読みたいところへジャンプできるよ!
この記事で解決できる悩み
こんな悩みを解決する記事を用意しました!
本記事では、建設コンサルタントの現場で実際に体験した苦悩や成功エピソードをもとに、「やめとけ」と言われる理由や、業界のリアルな現状を詳しく解説します。
- 現場での厳しい労働環境や数字・資料管理の難しさ
- 若手の離職率が高い理由とキャリアパスの不透明さ
- 年収アップのための具体的な方法や転職のコツ
この記事を読むことで、あなた自身の適性や将来のキャリア選択について明確な判断基準が得られ、安心して次の一歩を踏み出すためのヒントが満載です!
建設コンサルタントはやめとけ?その理由と現実
- 建設コンサルに向いていない人の特徴
- 建設コンサルタントの若手離職率は本当に高い?
- 建設コンサルタントの年収は?実際に稼げるのか
- 建設コンサルのデメリットとは?働く前に知っておくべきこと
- ついていけない?建設コンサルタントの過酷な現場とは
- 建設コンサルタントの24年問題とは?業界の未来を考察
- 建設コンサルタントの仕事はなくなる?将来性の不安
建設コンサルに向いていない人の特徴

建設コンサルタントの現場は、決して誰にでも向いているわけではありません。
実際に私自身が現場で働いていたとき、以下のような特徴を持った人はなかなか苦労すると感じました。
建設コンサルに向いていない人の特徴
- 細かい数字や資料の管理が苦手な人
日々の業務では、膨大なデータを正確に管理し、クライアントや関係部署に提出する必要があります。
数字や細かい指示に対して苦手意識があると、業務の効率が落ちることが多かったです。 - 対人コミュニケーションに自信がない人
プロジェクトには多くのステークホルダーが関与しており、会議や打ち合わせ、現場の関係者との連絡調整が欠かせません。
私は初めのころ、対人コミュニケーションが苦手だったため、何度も誤解が生じ、仕事が円滑に進まなかった経験があります。 - プレッシャーに弱い人
プロジェクトの締め切りや、予期せぬトラブルが頻繁に発生する環境では、ストレス耐性が求められます。
特に、クライアントからの厳しい要求に応えなければならない状況では、精神的な負担が大きくなります。
私自身、転職して最初の数年はこれらの課題に直面し、何度も心が折れそうになりました。
しかし、これを乗り越えるためには、自分の性格や適性を正直に見つめ直すことが大切だと痛感しました。
建設コンサルタントの若手離職率は本当に高い?

建設コンサルタントの若手離職率が高いという噂は、実際の現場でも感じることができました。
私が経験した部署では、入社後3年以内に退職する若手社員が少なくありませんでした。
3年以内に退職する会社の特徴
- ストレスと過重労働
プロジェクトのデッドラインに追われ、長時間労働が常態化している現場もあります。
特に若手社員は、経験不足からくるミスや、上司とのコミュニケーションの行き違いが原因で精神的なストレスを感じやすいです。 - キャリアパスの不透明さ
建設コンサルタントのキャリアは、専門知識と経験を積むことである程度安定してくるものの、初期段階では明確な指針が示されないことも多いです。
私自身、最初は将来への不安から転職を考えたこともありました。 - 現場の厳しさ
上司からのプレッシャーや、クライアントとの折衝で「自分はこのままで良いのか」と疑問を持つことが多々あり、結果として離職を決断するケースも見受けられました。
実体験として、私の周りにも「建設コンサルタントの若手は本当に離職率が高い」と嘆く同僚が多く、実際の数字以上に現場の空気は重かったと覚えています。
建設コンサルタントの年収は?実際に稼げるのか

建設コンサルタントの年収に関しては、一見高収入を謳っている企業も多いですが、実際には個人の能力や業務量、プロジェクトの規模によって大きく左右されます。
私が働いていた職場でも、成果主義の色が強く、個々のスキルに応じた報酬が支払われる仕組みでした。
以下の表は、私が過去に関わったプロジェクトで感じた年収や働き方の違いをまとめたものです。
| 項目 | 建設コンサルタント | 施工管理 |
|---|---|---|
| 残業時間 | プロジェクトによって変動 | 常に多い傾向にある |
| 年収の安定性 | 成果に応じて変動する | 契約社員も多く安定している |
| 体力的負担 | デスクワーク中心で軽め | 現場作業が多く大変 |
私自身、年収面で一定の成功を収めたと感じることもありましたが、
その分、業務のプレッシャーも大きく、精神的な負担と引き換えに報酬が上がる仕組みだったと実感しています。
建設コンサルのデメリットとは?働く前に知っておくべきこと

建設コンサルタントとして働く前に、ぜひ理解しておいてほしいデメリットをいくつか挙げます。
ここでは、私自身の経験や先輩たちの話から得たリアルな情報をお伝えします。
建設コンサルタントのデメリット
- 長時間労働が避けられない
繁忙期には、夜遅くまでオフィスに残ることも多く、家族やプライベートとの両立が難しいと感じました。 - プレッシャーのかかる環境
クライアントの期待や業界の動向に常に目を光らせる必要があり、精神的なストレスが溜まりやすいです。 - 情報のアップデートが必須
技術革新や法律改正など、常に新しい情報をキャッチアップしなければならないため、勉強を怠るとすぐに置いていかれる感覚に陥ります。 - 転職のタイミングが難しい
経験を積んでから転職する場合でも、次のキャリア選択が慎重にならざるを得ず、思い切って転職を決断するのは勇気が必要です。
これらの点から、建設コンサルタントの仕事は一見安定しているように見えても、実は多くのリスクと向き合っていることが分かります。
私自身、こうしたデメリットに直面しながらも、自己成長のために乗り越えてきた経験があります。
ついていけない?建設コンサルタントの過酷な現場とは

現場での仕事は、オフィスワークとは全く異なる厳しさがあります。
現場に出ると、計画通りに進まないトラブルや、急な変更要求が次々と舞い込み、体力だけでなく精神力も試されます。
実際、私が現場で経験した中で最も印象に残っているのは、急な天候の変化によって工期が大幅に遅延し、発注者から厳しい叱責を受けたことです。
現場の雰囲気は、常に「ついていけない」と感じる瞬間があり、こうしたプレッシャーに耐えるためには、チーム全体の協力と迅速な対応が不可欠でした。
建設コンサルタントのトラブル
- 予想外のトラブル
- 突然の天候不良
- 設計変更の連続
- 精神的・肉体的負担
- 緊急時の対応で深夜までの作業
こうした経験から、もし自分が本当にこの業界に向いているかどうか、しっかりと自己分析することが大切だと痛感しました。
建設コンサルタントの24年問題とは?業界の未来を考察

「建設コンサルタントの24年問題」というキーワードを耳にしたとき、多くの人は何のことかさっぱり分からないかもしれません。
実際、私も最初はその意味を理解するのに苦労しました。
しかし、業界の将来を考える上では避けて通れない重要な論点です。
24年問題とは、インフラの老朽化や更新時期が重なることによって、業界全体に大きな影響が及ぶ可能性があるという問題です。
厚生労働省「働き方改革関連法のあらまし」に具体的には、以下のような点が指摘されています。
24年問題の内容
- 老朽化した設備の更新負担
- 人材不足による技術継承の難しさ
- 国や自治体の財政圧迫による予算カット
私自身、プロジェクトの見直しや再計画に関わった際、24年問題のリスクを痛感しました。
特に、長期的な視点でキャリアを考えると、この問題が自分の将来にどう影響するのか、真剣に検討せざるを得ませんでした。
建設コンサルタントの仕事はなくなる?将来性の不安

業界内では、テクノロジーの進化や働き方の多様化が進む中、建設コンサルタントの仕事自体がなくなるのではないかという不安も根強く存在します。
実際、私が関わっていたプロジェクトでも、AIや自動化技術の導入が進む中で、従来の業務が大きく変わる兆しを感じたことがあります。
建設コンサルタントの仕事自体がなくなるのではないかと言われる理由
- 自動化による業務効率化
- データ分析の自動化
- レポート作成のシステム化
- 新たなスキルセットの要求
- IT技術やデジタルツールの活用
- 柔軟な対応力
このような変化に対応できるかどうかが、今後のキャリアにおける大きな分岐点になると感じています。
私自身、これまでの経験を踏まえ、新しい技術や知識の習得に努めた結果、現場での立ち位置を確保することができましたが、常に「将来性」の不安と向き合いながら業務を進める必要がありました。
建設コンサルタントはやめとけ?でも優良企業なら違う?
- 建設コンサルタントの優良企業はどこ?見極め方を解説
- 建設コンサルタントのブラック企業を避ける方法
- 建設コンサルでも結婚できない?ワークライフバランスを考える
- 建設コンサルタントの転職は可能?向いてる人・向いてない人
- 建設コンサルタントを辞めた人の後悔と次のキャリア
- 建設コンサルタントの年収を上げる方法とは?
- 建設コンサルに未来はある?今後の展望と生き残る道
建設コンサルタントの優良企業はどこ?見極め方を解説

すべての建設コンサルタント企業が同じではありません。
中には、社員の働きやすさやキャリア形成に力を入れている優良企業も存在します。
私が転職活動をしていたとき、いくつかのポイントをチェックすることで、優良企業を見極めることができました。
建設コンサルタント企業の見極めるポイント
- 企業の経営方針やビジョンの明確さ
- 従業員の定着率と福利厚生の充実度
- 社内のコミュニケーションの円滑さ
これらの点を踏まえ、実際に企業の口コミや内部の情報を集めることが非常に重要です。
私が面接を受けた企業の中には、福利厚生が整っており、キャリアアップ支援が充実していたところもありました。
こうした企業は、ブラック企業と呼ばれるような環境とは一線を画していると感じました。
建設コンサルタントのブラック企業を避ける方法

ブラック企業に入ってしまうと、前述のような過酷な労働環境にさらされる危険性が高まります。
実際、私の知人もブラック企業での過酷な労働に耐えかね、転職を余儀なくされたケースがありました。
そこで、ブラック企業を避けるためのポイントをまとめました。
ブラック企業を避けるためのポイント
- 企業の口コミサイトやSNSで情報収集を徹底する
- 面接時に働き方や評価制度について詳しく質問する
- 労働環境や残業時間について、現役社員の意見を参考にする
これらの方法を実践することで、事前にリスクを回避できる可能性が高くなります。
建設コンサルでも結婚できない?ワークライフバランスを考える

業界内では、長時間労働や休日出勤が原因で「結婚できない」との噂もあります。
私自身はそんなことはありませんでした。(結婚しましたし。)
一緒に働いている方に聞いたところ、建設コンサルタントの会社によって忙しさがまちまちのようです。
ホワイトな建設コンサルタントの特徴
- 労働時間の実態と改善策
- 定時退社を目指す取り組みがある
- リモートワークの導入状況
- 家庭との両立に成功した先輩がいる
- 柔軟な働き方を実現する企業文化
- 育児支援制度の充実
こうした事例を参考にしながら、今の働き方を見直すきっかけになりました。
むしろ、建設コンサルタントに転職後にワークライフバランスが改善し、結婚や家庭生活にも前向きに取り組めるようになりました。
建設コンサルタントの転職は可能?向いてる人・向いてない人
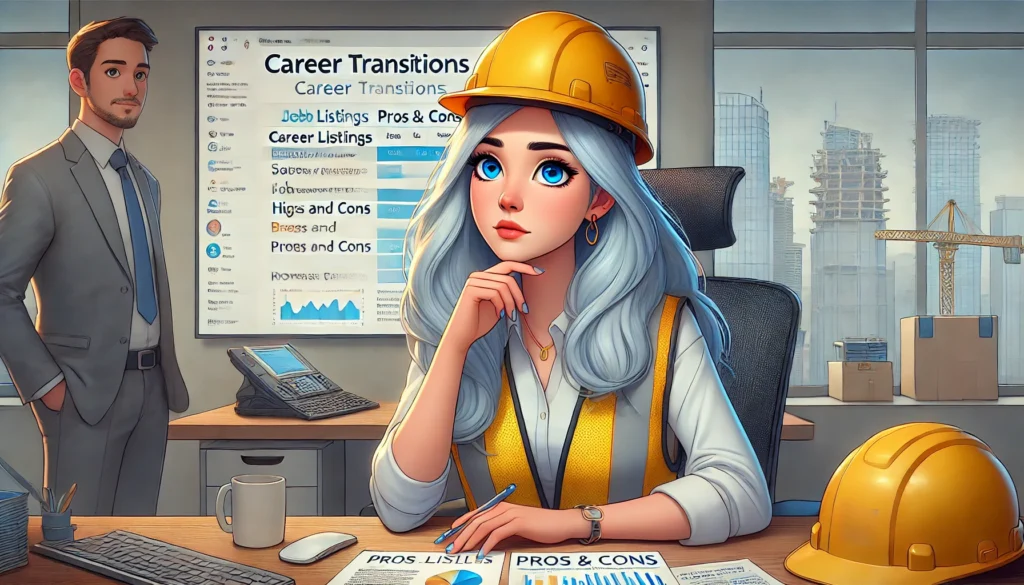
転職市場においても、建設コンサルタントは特殊なスキルが求められるため、向いている人と向いていない人がはっきり分かれることが多いです。
以下の表は、転職の際に考慮すべきポイントをまとめたものです。
| 項目 | 向いている人 | 向いていない人 |
|---|---|---|
| コミュニケーション | 積極的に意見を交わせる人 | 一人で作業するのが好きな人 |
| ストレス耐性 | 緊急時にも冷静に対応できる人 | プレッシャーに弱い人 |
| 学習意欲 | 新しい技術や知識に貪欲な人 | 現状維持を望む人 |
私自身、転職活動を通じて、自分がどちらに属するのかを明確に理解することができ、結果として適した企業に出会えた経験があります。
建設コンサルタントを辞めた人の後悔と次のキャリア

現役時代、私の周囲には「もう二度とこの業界には戻らない」と断言する人もいれば、転職後に新たなキャリアを見つけ、充実した生活を送っている人もいました。
後悔と感じる理由としては、過酷な労働環境や評価制度の不透明さが挙げられます。
建設コンサルタントをやめる理由
- 長時間労働による健康面のリスク
- 将来性に対する不安から来る精神的ストレス
- 次のキャリアとして選んだ方向性
建設コンサルタントの次の転職先の例
- IT業界やデジタル技術に転向
- コンサルタント経験を活かし、フリーランスとして活動
- 異業種への転職による新たな挑戦
私自身も一度はこの業界から離れる決断をしましたが、
その後、新たな環境で自分のスキルを活かし、充実感を得ることができました。
後悔と成功の両面が混ざり合った複雑な体験でしたが、今ではすべてが成長の糧になっていると実感しています。
建設コンサルタントの年収を上げる方法とは?

年収アップを目指すためには、いくつかの戦略が必要です。
私が実際に試みた方法をいくつかご紹介します。
建設コンサルタントが年収アップを目指すために
- 専門資格の取得
業界内で評価される資格を取得することで、報酬のアップに直結するケースが多いです。 - プロジェクトのマネジメント経験を積む
経験を積むことで、責任あるポジションに就くチャンスが増え、結果的に年収が上がります。 - ネットワークの拡大
業界内外の人脈を広げることで、新たなビジネスチャンスや情報が得られます。 - 転職活動の実施
定期的に自分の市場価値を見直し、より良い条件の企業を探すことも重要です。
これらの方法は、私自身が実際に取り組んできたもので、効果を実感できた戦略ばかりです。
年収に直結するスキルアップは、個人の努力と環境の両面から考える必要があると感じています。
建設コンサルに未来はある?今後の展望と生き残る道

今後の建設コンサルタント業界は、テクノロジーの進化や市場環境の変化に伴い、大きく様変わりする可能性があります。
私が関わっていたプロジェクトでも、デジタルツールの導入が進み、従来の業務プロセスが大幅に改善される兆しを感じました。
建設コンサルタントの今後
- 技術革新の影響
- 自動化による効率アップ
- ビッグデータ解析を活用した予測精度の向上
- 市場の変化
- インフラ老朽化に伴う更新需要の増加
- 環境対策や持続可能性に関する新たな要求
こうした変化に対応できるかどうかが、各企業の今後の生き残りに直結すると考えています。
私自身、最新技術の習得に努めた結果、変革期においても現場での存在感を保つことができた経験があり、今後も変化に柔軟に対応する姿勢が求められると実感しています。
建設コンサルタントはやめとけ?最終結論と判断基準

建設コンサルタントはやめとけ?最終結論と判断基準
最終的に、建設コンサルタントとして働くか否かは、個々の適性やキャリアプランに大きく依存します。
私自身、実際の現場での厳しい経験を経て、時には「建設コンサルタント やめとけ」と思う瞬間もありましたが、
その一方で多くの学びや成長を得ることができたと感じています。
建設コンサルタントはやめておいた方がいいと言われる理由
- 自己分析の重要性
- 自分のスキルやストレス耐性を正しく評価することが不可欠です。
- 業界の未来と自分の成長のマッチング
- 24年問題や技術革新など、業界全体の動向を把握し、自分がどの位置にいるかを判断する必要があります。
- キャリアチェンジの柔軟性
- 転職や業界内でのポジション変更が、さらなる成長のチャンスとなり得ます。
私の経験から言えば、建設コンサルタントとして働くことで得られるスキルや知識は非常に価値がある一方、厳しい現実も多く存在します。
もし自分が現場のプレッシャーや長時間労働に耐えられると確信できるなら、挑戦する価値は十分にあるでしょう。
しかし、そうでない場合は、他のキャリアパスを模索することも一つの賢明な判断です。
実際に私も、転機を迎えたときに自分の内面と向き合い、適切な選択をすることで、今の充実した働き方につながりました。
この判断基準をもとに、自分自身の今後のキャリアをじっくり考える時間を持つことが、最終的な成功への近道になるはずです。
「いきなり転職するのは不安…」と感じる方も、面談だけならリスクゼロ!
まずは話を聞いてみることから始めてみてください。
✅ 今すぐ【Re就活エージェント】の詳細を見る















コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 建設コンサルタントのリアル!「やめとけ」と言われる理由と対策 読みたいところへジャンプできるよ! この記事で解決できる悩み […]