「ゼネコン ブラックすぎる・・・」「中堅ゼネコンはもしかして、やばい?・・・」と思ってしまうほど、
長時間労働や現場の逼迫感に心身がすり減っていませんか?
評価されない残業、終わらない工程、改善が進まない現場──
このままでいいのかという不安が、じわりと胸を締め付けます。
しかし、こうした状況の裏側には、
業界全体の構造的課題や、大手・中堅ゼネコン共通のボトルネックが潜んでいます。
労働時間規制が強まっても「なぜ現場は変わらないのか?」
その理由を知らないままだと、いくら頑張っても報われないままです。

この記事でわかること
- 労働時間規制後も建設業界に残る根本的な構造課題
- 不祥事や評判から読み取れる共通リスクと業界特性
- 年収・残業時間・離職率など、一次データの正しい読み解き方
- 休日増やす/残業減らすための転職・環境改善の実践ステップ
私自身、建設業に10年務めた経験から、
ブラック化しやすい現場の特徴や、改善が進みにくい理由を痛感してきました。
だからこそ、主観ではなく一次情報にもとづく視点が必要だと断言できます。
本記事では、不祥事の構造やデータの読み解き方、
そして休日を増やし、残業を減らしながらステップアップするための
“現実的な選択肢” を整理しています。
読み終える頃には、いまの状況を客観視し、
環境を変えるための確かな判断軸が手に入るはずです。
診断
あなたに最適な建設業転職エージェントは?
4つの質問で診断!あなたにぴったりの転職エージェントが分かります。
まずは、この記事を“比較材料”として活用してください。
迷ったときにまた見返せるよう、ブックマークも推奨します。
あなたの働き方が、今日から少しずつ変わりますように。
まだゼネコンブラックすぎる?環境は本当に変わるのか
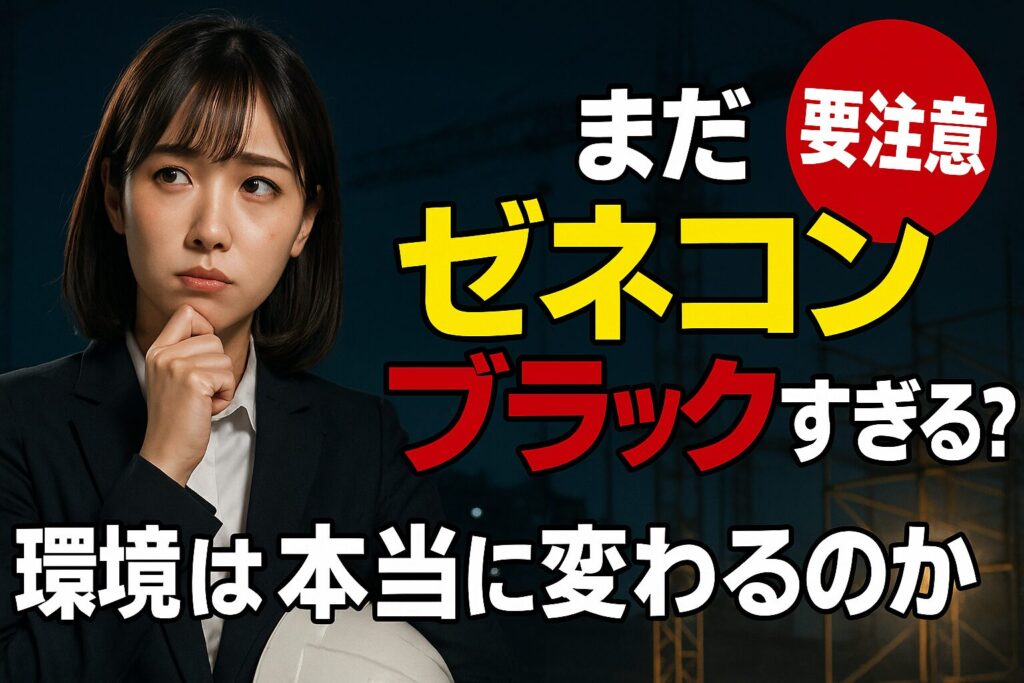
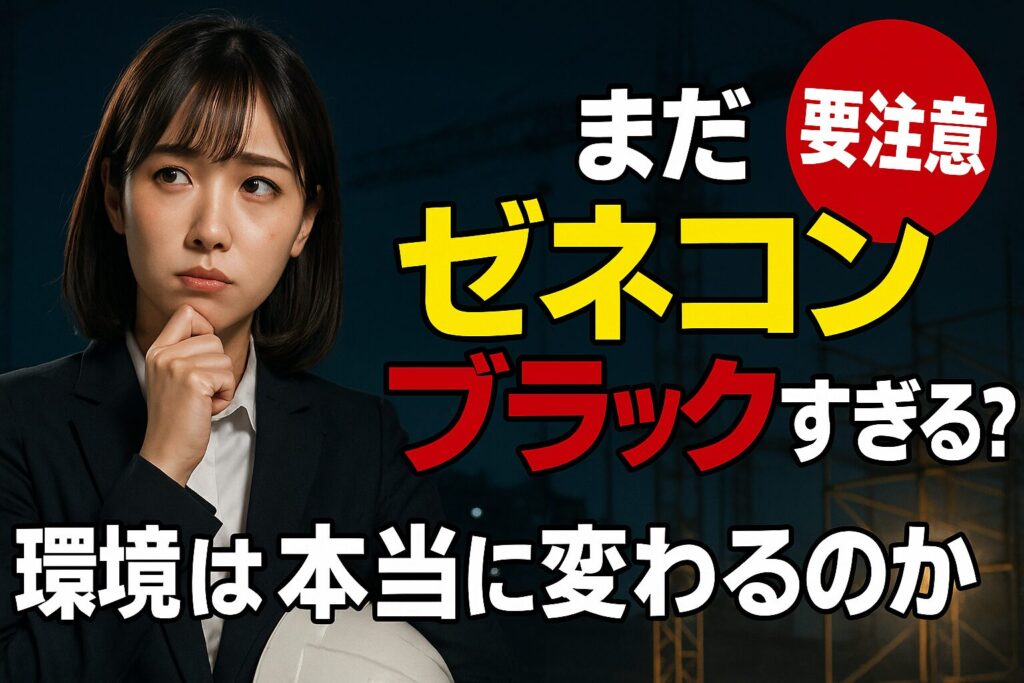



この章でわかること
- なぜやばいと言われ続けるのか徹底解説
- 大手ゼネコンやばい実態は想像以上なのか?
- 中堅ゼネコンやばい現場が放置される理由とは
- ゼネコン不祥事ランキングから見える衝撃構造
- 評判の悪いゼネコン特徴に当てはまる危険サインは?
- 平均年収平均残業時間ブラック化の真相とは
- 離職率ゼネコンで深刻化する人材流出問題
なぜやばいと言われ続けるのか徹底解説
建設業界は、工期・品質・安全・コストという四つ巴の制約を同時に満たす必要があり、さらに天候リスクや地中障害といった不可抗力が常に潜むため、工程の遅延吸収が難しい産業構造を持っています。元請から下請、さらに再下請へと続く多重下請の分業が一般的で、情報と責任が階層的に分散される一方、現場の最終責任は施工管理に集中しやすいという歪みが生まれます。結果として、発注条件が厳しいほど工程後半に負荷が偏り、残業や休日出勤が膨らみやすい土壌が形成されます。
2024年には時間外労働の上限規制が建設業にも全面適用され、原則月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間以内などの枠が定められています。制度設計により過剰な長時間労働の抑制が期待される一方、実務では工期短縮要請や設計変更、サプライチェーンの遅延が重なると、「規制を守りながら工程を成立させる」ための計画力と人員余力が問われます。特に重機据付やコンクリート打設などのクリティカル工程は、品質確保の観点から時間あたりの生産性の上限があり、単純な人手投入では対応できない局面が存在します。
もう一つの論点は、週休二日化と技能人材の逼迫です。週休二日が導入されても、資材納期や発注側の検査日程が固定化されたままでは、現場のカレンダーに余白が生まれません。技能労働者の高齢化や若年入職の減少も重なり、「限られた人数で品質を落とさずに生産性を上げる」という高度なマネジメントが常時求められます。BIM/CIMによる出来形管理やドローン測量、配筋検査のデジタル化などの施策は改善効果を示しつつありますが、全社横断での標準化と教育が伴わないと現場間のばらつきが残ります。
要点:制度は上限を定めたが、発注条件・設計変更・人員構成・技能の伝承という前提が変わらない限り、現場の体感改善は段階的にしか進まない。工程計画と品質マネジメントの高度化がカギ
用語解説:クリティカルパス(工事全体の工期に直接影響する工程の連鎖)。この連鎖の余裕時間がゼロの区間が長いほど、遅延の吸収余地が小さく、時間外労働が発生しやすい構造になる
制度根拠は厚生労働省の公表資料で確認できます(出典:厚生労働省 時間外労働の上限等リーフレット)。
大手ゼネコンやばい実態は想像以上なのか?
規模の大きい企業はリソースを潤沢に抱えるイメージがありますが、超高層・大規模再開発・大型インフラといった高難度案件では、設計・調達・施工・試運転のどの段階でも想定外が生じ得ます。設計変更に伴う施工図の更新、資材の代替選定、サブコンとの工程再調整、行政協議のやり直しなど、ひとつの変数が連鎖反応を起こし、「品質を落とさずに工期とコストを守る」という至上命題が一気に厳しさを増します。加えて、足場・揚重・搬入路・周辺交通といった物理的制約は金銭で即座に解決できないため、現場のオペレーションは複雑化します。
品質不具合が顕在化した事案では、計測・試験・出来形のデータ管理と、是正のリカバリープランの実行力が問われます。鉄骨建方のボルト孔位置の精度不良や、床レベルの許容差逸脱といった不具合が確認されると、補修の可否判断・安全性評価・第三者検証・関係者説明と、工程外のタスクが一挙に積み上がります。これらは現場要員の時間資源を直接圧迫し、デスクワーク比率を高め、結果として所定外労働の増加につながりやすくなります。
大手に共通する打ち手としては、設計段階のBIM連携強化、購買の先行手配、サブコン横断の標準ディテール化、検査プロセスのデジタル化が挙げられます。現場におけるモックアップ検証や、要領書・安全手順書のテンプレート化、品質記録のクラウド一元化は、是正工事の発生確率と影響度を同時に抑えるのに有効です。一方で、これらは初期費用と教育負荷を要するため、全社的に定着させるには時間がかかります。
注意:特定企業や特定案件の評価は、最新の公式開示・第三者報告で随時更新されます。本稿は一般化可能な構造とプロセスの観点を述べたもので、個別企業の将来見通しを示すものではありません
実務ポイント:品質起点の工程計画(品質ゲートでの合否と次工程の連動)、出来形の許容差・試験頻度の事前合意、代替材承認のリードタイム把握が、所定外の膨張を抑える基本線
中堅ゼネコンやばい現場が放置される理由とは
中堅規模の企業は、意思決定の速さや現場密着の強みを持つ一方、同時に抱えられる大型案件の数やバックオフィス機能に限界が生じやすい側面があります。工事部門・設計部門・購買部門の人員が薄く、ひとりの担当者が複数の重要工程を兼任する状況では、トラブル時の代替策立案と承認プロセスが滞りがちです。さらに、再下請まで連なる多重下請構造では、情報の遅延や伝達の齟齬が起きやすく、軽微な手戻りが累積して工程末期に顕在化することがあります。
規制適用後は、特別条項の運用回数や限度が明確化され、紙の上では時間外の歯止めがかかります。しかし、「工程の余白が薄い」「代替要員がいない」「資材調達の選択肢が少ない」といった制約が複合すると、期末の突貫作業が規制の枠内に収まりにくくなります。ここで重要になるのが、発注者との初期段階での合意形成です。設計確定のマイルストン、承認フローの期日、仕様変更時の工期・費用補償などを契約・覚書に織り込むことで、工程後半のリスク転嫁を避けられます。
中堅の現場で放置されやすい課題としては、安全投資と教育の後回し、品質検査の属人化、支払サイトの長期化による協力会社の資金繰り悪化が挙げられます。これらは短期的なコスト圧縮には見えても、中長期では離職や技能流出、品質事故のリスク増といった大きな負債になります。対策はシンプルで、毎日のKY(危険予知)を形式化ではなく実効化し、ヒヤリハットの共有を積み重ねること、品質検査の項目・頻度・合否基準を標準化してクラウドで記録すること、協力会社への価格転嫁と迅速支払いで人員確保の土台を整えることです。
改善の勘所:契約初期の仕様凍結と承認カレンダー、主要資材の早期内示と複線調達、要員のバックアップ体制、作業所DX(出来形写真の自動整理・検査ワークフローの見える化)を最小セットとして導入する
用語解説:出来形管理(完成物の寸法・形状が設計値を満たすかを測定・記録する管理)。写真・測量・試験成績で客観化し、後工程や引渡し時の品質証跡とする
ゼネコン不祥事ランキングから見える衝撃構造
不祥事のニュースが話題化するとき、単発のミスや現場の一過性の問題として片づけられがちですが、建設業では「受注競争の激化」「多重下請」「工程の硬直」「記録と監査の非デジタル運用」といった構造が同時に作用することで、発覚の契機と影響の拡大が生まれやすくなります。たとえば、入札や発注での公正性が疑われる事案は、現場の努力だけでは是正できない領域であり、コンプライアンスと調達ガバナンスの設計が企業風土として定着しているかが試されます。品質不適合やデータ改ざんが表面化するケースでは、出来形・試験・計測の根拠資料が紙や表計算の分散管理に留まっていると、遡及的な追跡が困難になり、初動対応が遅れて被害範囲が広がります。
再発防止の観点では、落札・契約・工程・品質・支払というバリューチェーンの各段で独立した牽制が効いているかが重要です。調達ではベンダー選定の理由付けと価格の根拠、工程ではクリティカルパスの合意、品質では検査頻度と判定基準の標準化、支払では変更契約と出来高査定の透明性が、相互に連動する必要があります。さらに、内部通報制度が機能している企業は、現場の小さな違和感が経営に伝わりやすく、重大事案に至る前に是正できる余地が広がります。KPIとしては、是正の初動までの平均日数、再発率、外部監査の指摘密度、変更契約の締結リードタイムなど、行動に直結する指標を用いると、単なる「教育実施回数」より有効です。
実務で効く再発防止の型:入札・契約段階での利益確保の目線を明文化、工程ゲートごとの品質記録と写真の自動紐付け、変更契約の稟議をワークフロー化、内部通報の匿名性と調査独立性を制度化
用語解説:内部統制(企業の業務の有効性・財務報告の信頼性・法令遵守を確保する仕組み)。建設では購買・原価・工程・品質・安全の各プロセスに統制点を設け、職務分掌(相互牽制)で機能させる
独占禁止法違反に関する一次情報は、公正取引委員会の公式発表で確認できます(出典:公正取引委員会 報道発表)。
不祥事が発生しやすいプロセスの可視化
| 局面 | 起こりやすい事象 | 有効な牽制 |
|---|---|---|
| 入札・契約 | 価格調整・不透明な仕様変更 | 入札記録の保存、第三者同席、根拠文書の標準化 |
| 工程管理 | 突貫・検査省略・記録遅延 | 品質ゲートと次工程の連動、遅延アラート |
| 品質管理 | 出来形逸脱・試験省略 | 自動時刻付き写真、第三者試験、追跡ID |
| 変更・支払 | 未契約作業・後追い精算 | 変更契約の起票必須化、出来高査定の可視化 |
注意:いわゆる「ランキング」は集計基準で印象が変わります。単純比較ではなく、再発防止策の質・初動速度・情報開示姿勢といった行動指標を重視してください
評判の悪いゼネコン特徴に当てはまる危険サインは?
志望先の見極めでは、求人票やパンフレットの美辞麗句よりも、制度設計と現場運用の一致度を測る質問が効果的です。例えば、週休二日をうたっていても、工程表に休日の明確なブロックがない、検査日や発注者協議が休日に配置される、といった矛盾があれば、制度が実務に落ちていない可能性があります。残業上限の管理も、36協定の枠だけでなく、月別の実績推移・部署別のばらつき・特別条項の発動回数まで開示があるかで見え方が変わります。協力会社への支払い条件(支払サイト・前払・設計変更時の増額手当)も、人員確保と品質安定に直結するため重要です。
安全・品質・コンプライアンス・人事の四分野で、チェック観点をあらかじめリスト化しておくと、面接での深掘りがスムーズになります。安全では教育・点検・第三者監査の頻度、品質では検査の判定基準とモックアップ運用、コンプライアンスでは内部通報制度の独立性、人事では評価指標に「長時間是正・休日確保」を組み込んでいるかが判断材料になります。さらに、BIM/CIMや出来形のデジタル記録が標準化されているか、クラウドの工事写真管理で検索・追跡が容易か、などの現場DXは、残業の源を減らす実装力の指標にもなります。
面接で使える質問例
- 週間工程に休日ブロックは固定されていますか。発注者協議や検査は平日に限定されていますか
- 36協定の特別条項は年に何回運用しましたか。部署別の月残業実績は開示可能ですか
- 出来形・試験記録はクラウド一元管理ですか。写真と検査票は自動紐付けされていますか
- 内部通報は第三者窓口ですか。通報から初動までの平均日数はどれくらいですか
- 協力会社の価格転嫁と前払条件は明文化されていますか。支払サイトは何日ですか
| 領域 | 危険サイン | 望ましい状態 |
|---|---|---|
| 制度と運用 | 休日や残業の運用が部署でバラバラ | 部署横断の基準と公開ダッシュボード |
| 教育 | 安全・品質教育が形式的 | 受講後テストと現場実技のセット運用 |
| 品質 | 検査基準が属人的で記録が散在 | 標準化された合否基準とクラウド記録 |
| 調達 | 設計変更時に価格増が反映されない | 変更契約と出来高査定の時点反映 |
| 通報 | 内部通報窓口が人事部門に固定 | 外部窓口と匿名保護、報復禁止の明文化 |
注意:ネット上の評判は母集団と時期で偏ります。一次情報(制度文書・実績数値・監査報告)と照合し、単発の口コミで判断しないことが重要です
平均年収平均残業時間ブラック化の真相とは
年収だけで働きやすさを判断すると、残業時間の長短や休日制度の運用差を見落としがちです。建設業はプロジェクト型の性質上、繁忙期と閑散期の差が大きく、年収が同じでも月あたりの可処分時間に大きな差が出ます。加えて、固定残業(みなし残業)の設定や、現場手当・出張手当の付与条件、深夜・休日労働の割増計算の扱いによって、手取りと体感が変わります。重要なのは、「年収÷年間実労働時間」という実効時給の観点で比較することです。面接では、月別の残業実績と休日取得、みなし残業の時間数・超過時の精算ルールまで確認しておくと、入社後のギャップを抑えられます。
残業時間の削減は、単純に人員を増やすだけでなく、非付加価値作業の圧縮が効果的です。具体的には、写真整理や出来形チェック、検査記録の二重入力、図面の版管理、協力会社との往復承認など、事務的な負荷をデジタルで置き換えることが、体感の短縮に直結します。BIM/CIMの属性情報を積極的に活用し、現場での寸法・数量の突合作業を短縮する、RFI(問い合わせ)をワークフロー化して回答の合意形成を早める、といった取り組みは長時間化の源流を断つのに有効です。さらに、週休二日化を実効化するには、土曜の工程ブロック化と資材搬入・検査の平日固定が欠かせません。
比較のためのフレーム
| 項目 | 確認ポイント | 見極めの視点 |
|---|---|---|
| 年収 | 固定残業の時間数・上限超の精算 | 実効時給で横串比較 |
| 残業 | 月別実績と部署間のばらつき | 繁忙・閑散の波と人員の弾力性 |
| 休日 | 年間休日・週休二日の実運用 | 工程と検査の平日固定度合い |
| DX | 写真・検査・図面の一元管理 | 非付加価値作業の削減効果 |
| 支援 | 協力会社への価格転嫁と支払 | 人員確保の安定性 |
用語解説:RFI(設計照会)。設計の不明点を施工側が正式に問い合わせ、回答を記録して設計変更や現場指示に反映するプロセス。記録の一元化で手戻りと紛争を回避しやすくなる
注意:統計の年収・残業は母集団や職種構成で大きく変動します。最新の公的資料や企業の有価証券報告書・統合報告書における開示の読み合わせを推奨します
離職率ゼネコンで深刻化する人材流出問題
建設業の人材流出は、単に「離職率が高い」という問題ではありません。
業界の構造、技能者の高齢化、人口減少など、さまざまな要因が複雑に重なっています。厚生労働省の調査では、建設業の新卒3年以内離職率は35.6%とされていますが、この数字だけで「ブラックだから辞める」と判断するのは早計です。
特に施工管理職は、現場調整・安全管理・品質管理など多くの判断が求められます。
現場では年代の違う技能者へ指示を出す必要があり、入社初期からコミュニケーション負荷が大きく、精神的なストレスにつながりやすいのが現状です。また、建設業の「プロジェクト型」の働き方は成果が見えるまで時間がかかり、成長実感を得にくいこともモチベーション低下の原因になります。
一方で、離職を抑えられている企業には共通点があります。
現場支援部門による定期的なフォロー、無理のない工程計画、週休二日制の徹底、協力会社への適切な価格転嫁など、「現場に負担が偏らない仕組みづくり」ができています。さらに、配筋検査や型枠などの技術教育が体系化されている企業では、若手が自信を持ちやすく、ストレス耐性も高まります。
最近では、デジタル化による業務効率化も離職防止につながっています。
写真整理、図面管理、検査帳票の作成など、本質的でない作業が属人化している現場ほど残業が増えがちです。その対策として、クラウド施工管理アプリや検査写真の自動紐付け、RFI(設計照会)のオンライン化などを導入し、実際に残業削減が進んでいる企業もあります。
離職の原因
- 現場のフォロー体制が弱い
- 週休二日が守られていない
- 非効率作業が多く残業が増えやすい
- 協力会社の人員不足が放置されている
- 教育制度が整っていない
また改善する評価指標に「安全・品質KPI」を組み込む大きく変動します。単年数値ではなく、複数年度の推移を見ることが重要です
改善の鍵
- 配属後6ヶ月以内の面談やメンター制度
- 週休二日の徹底(検査は平日固定)
- 図面管理や写真整理のDX化
- 協力会社への適正価格転嫁&早期支払い
参考として、離職率に関する一次情報は厚生労働省の雇用動向調査で確認できます(出典:厚生労働省 雇用動向調査)。
ゼネコンブラックすぎる未来を避ける選択肢とは?





この章でわかること
- ゼネコン激務ブラックのサイクルはなぜ止まらない?
- 休日増やす残業減らす転職が最適解なのか?
- ステップアップどうする?後悔しない選び方の核心
- ゼネコンブラックすぎる状況から抜け出すまとめと提案
ゼネコン激務ブラックのサイクルはなぜ止まらない?
現場の激務が続く理由は、単に仕事量が多いからではなく、「負荷が後工程へ集中する構造」にあります。建設工事では、設計決定・資材承認・工程調整の遅れが初期に発生しやすく、そこでは課題が見えにくいため、終盤の仕上げ工程にしわ寄せが起こります。この遅れを回収するための突貫は、長時間労働・休日出勤の原因になります。
また、協力会社の人員不足が進み、繁忙期の要員確保が困難になっている点も激務化の一因です。技能者の高齢化が進行する中、若手の入職は伸び悩み、結果として需要と供給のバランスが崩れています。
さらに、発注者側の業務設計や検査スケジュールが硬直的である場合、現場は短期集中のピークを強いられます。作業所内で調整できない外部制約が強いほど、計画に柔軟性がなくなり、遅延の吸収余地が縮小されます。
激務の原因
- 設計変更・仕様決定の遅延
- 代替の効かない技能者の不足
- 発注スケジュールの硬直化
- 検査・評価制度の属人化
- 非付加価値作業の多発
この構造から脱却するためには、初期段階の設計凍結、承認ワークフローの短縮、BIMによる干渉チェック、週休二日化の工程カレンダー適用が有効です。また、若手の現場OJT(実務訓練)だけでなく、体系的教育の併用がミスの減少と再作業の回避につながります。
休日増やす残業減らす転職が最適解なのか?
環境を変える手段として、転職は現実的かつ効果の高い選択肢です。現場の制度や文化は短期的には変えづらく、「所属先を変える」ことが最速の改善策になるケースは多く見られます。特に、週休二日制度が定着している企業や、作業所DXを標準化している企業では、残業抑制と休日確保の両立が進んでいます。
ただし、「大手=優良」「中堅=ブラック」と安易に分類するのは危険です。重要なのは、制度の有無よりも運用の実態です。求人票に週休二日と書かれていても、工程上の制約によって週休一日運用が常態化している現場もあり、実態を確認しなければ判断できません。



転職面接で確認すべき質問
- 残業時間の部署別・月別実績
- 36協定の特別条項発動回数
- 週休二日の現場カレンダー適用率
- 設計変更時の追加費用補償の有無
- 協力会社への価格転嫁指針
ポイント:評価制度に「長時間抑制」「休日確保」の項目がある企業は、継続的に働き方が改善されやすい傾向がある
注意:口コミは個人の主観が強く、時期によって偏りがあります。一次情報(制度文書・内部監査報告・現場実績)で裏付けることが重要です
長時間労働への規制は厚労省資料で確認できます(出典:厚生労働省 時間外労働の上限規制)。
ステップアップどうする?後悔しない選び方の核心
後悔しないキャリアづくりで大切なのは、環境を変えるだけでなく、将来の選択肢を増やすことです。施工管理で培う工程・品質・安全・コストの知識は、設備・電気、リニューアル、発注者支援、施設管理、BIM担当などへ幅広く展開できます。
その第一歩は、今の仕事での成果を再現できる実績として言語化しておくこと。成果指標 × 実施した施策 × 再現条件をセットで語れると、配属でも転職でも評価されやすくなります。



実績の作り方
- 課題をどう定義したか(安全・品質・工程・コストのどれか)
- どんな施策を打ったか(施工計画の見直し、干渉チェック、要員平準化など)
- どの条件で再現できるか(手順、関係者合意、必要リソース)
- 数値で示せるか(工期短縮○%、手戻り△件減、残業▲時間削減 など)
進む方向によって「働き方のクセ」も大きく変わります。自分が何を優先したいか(収入・安定・学び・裁量など)を軸に比較しましょう。
案件ごとの特徴
| 選択肢 | 強み | 留意点 | 相性が良い経験 |
|---|---|---|---|
| 新築大規模 | 達成感・報酬が高め | 終盤のピークが大きい | 工程平準化・サブコン統括 |
| リニューアル | 範囲が明確で計画しやすい | 夜間・短期が増えやすい | 仮設計画・安全計画 |
| 設備・電気 | 体系化されDXと相性抜群 | 専門学習の負荷がある | 図面整合・試運転計画 |
| 発注者支援(CM/PM) | 全体最適・交渉力を活かせる | 現場との距離が生じやすい | 契約管理・変更合意 |
| 施設管理(FM) | 長期の安定・計画性 | 24h体制の可能性 | 保全計画・更新提案 |
BIM/CIMのスキルは今後の強力な武器です。3Dモデルを工程(4D)やコスト(5D)と結び、干渉検出・数量拾い・出来形照合までつなげると、ムダ作業の削減とリスクの早期発見に直結します。
用語メモ:4D/5D(四次元・五次元BIM)=3Dモデルに工程やコストの情報を付与してシミュレーションする考え方。意思決定のスピードと精度を上げるのが狙い
社内で進路が見えにくいときは、社外の選択肢も検討に値します。発注者側、監理、コンサル、FMなど、施工管理の基礎は横展開が可能です。どの道でも、「成果指標 × 施策 × 再現条件」を言語化しておくことが説得力を高める近道です。
注意:資格要件やBIMの実務基準は更新されます。応募前に募集要項と最新の公的情報を必ず確認してください。
ゼネコンブラックすぎる状況から抜け出すまとめと提案



この章でわかること
- 制度の有無ではなく運用の実態を数字で確認し配属差も含めて判断する
- 週休二日の工程ブロック化と検査の平日固定が体感改善の土台となる
- RFIや変更契約のリードタイム短縮で終盤の突貫リスクを下げる
- 出来形と写真の自動紐付けで品質証跡を整備し再作業を抑制する
- 協力会社への価格転嫁と迅速支払が人員安定と品質維持に直結する
- 36協定の特別条項運用回数と部署差を質問し透明性を確認する
- 年収ではなく年労働時間で実効時給を算出し比較軸を揃える
- BIMCIMの実務活用を学び干渉検出と数量拾いに展開する
- 安全と品質のKPIを評価制度に組み込み長時間是正を促進する
- 内部通報の匿名性と独立性を確保し初動の早さを指標化する
- 新築とリニューアルの案件特性を理解し自分の適性で選ぶ
- 転職面接では部署別残業実績と休日取得率の数値開示を求める
- 教育とOJTの両輪で若手の自律度を高め離職を抑える
- 発注条件の明確化と設計凍結の合意で後工程の余白を確保する
- キャリアは専門性と持続可能性の交点で設計し機会を拡張する
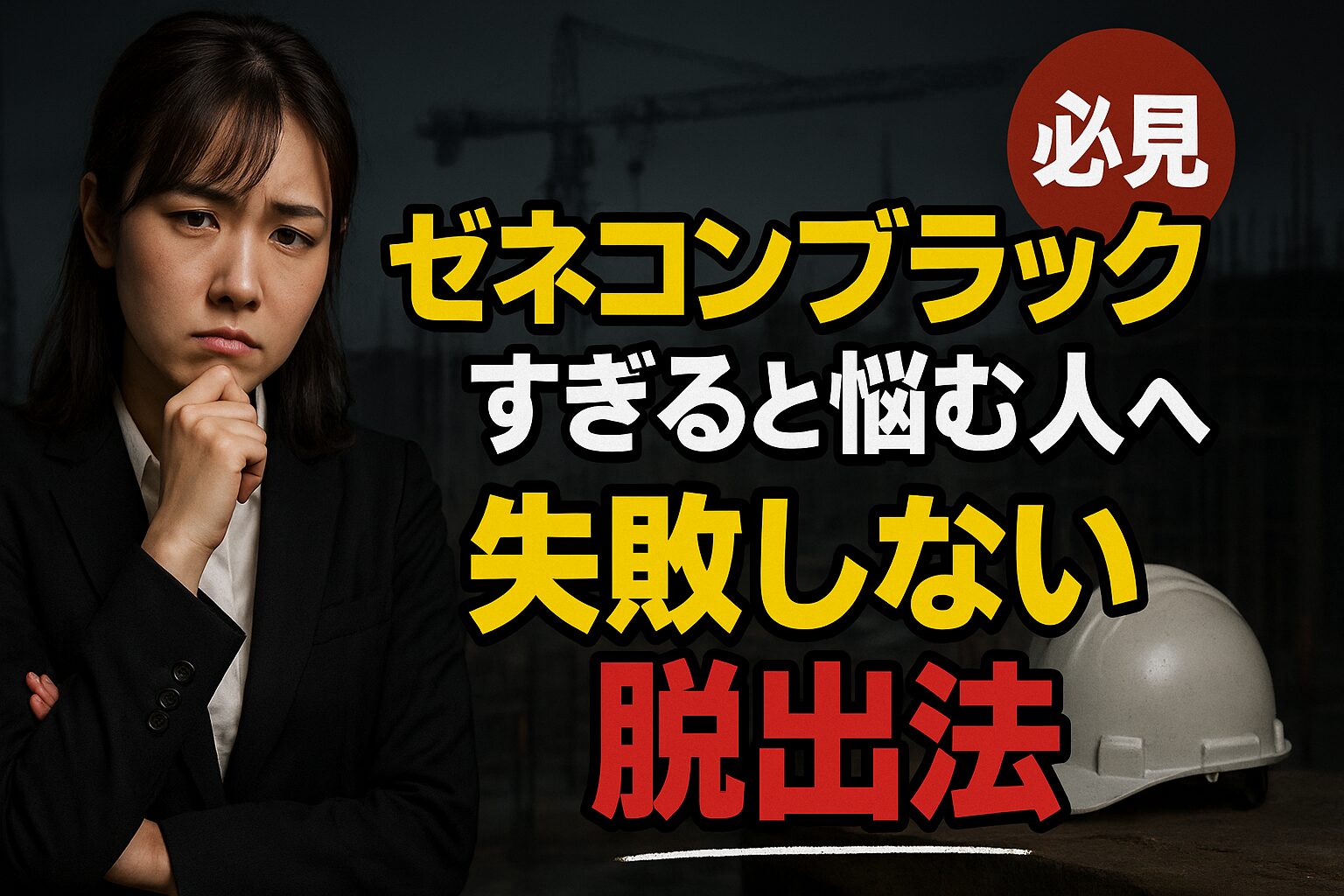
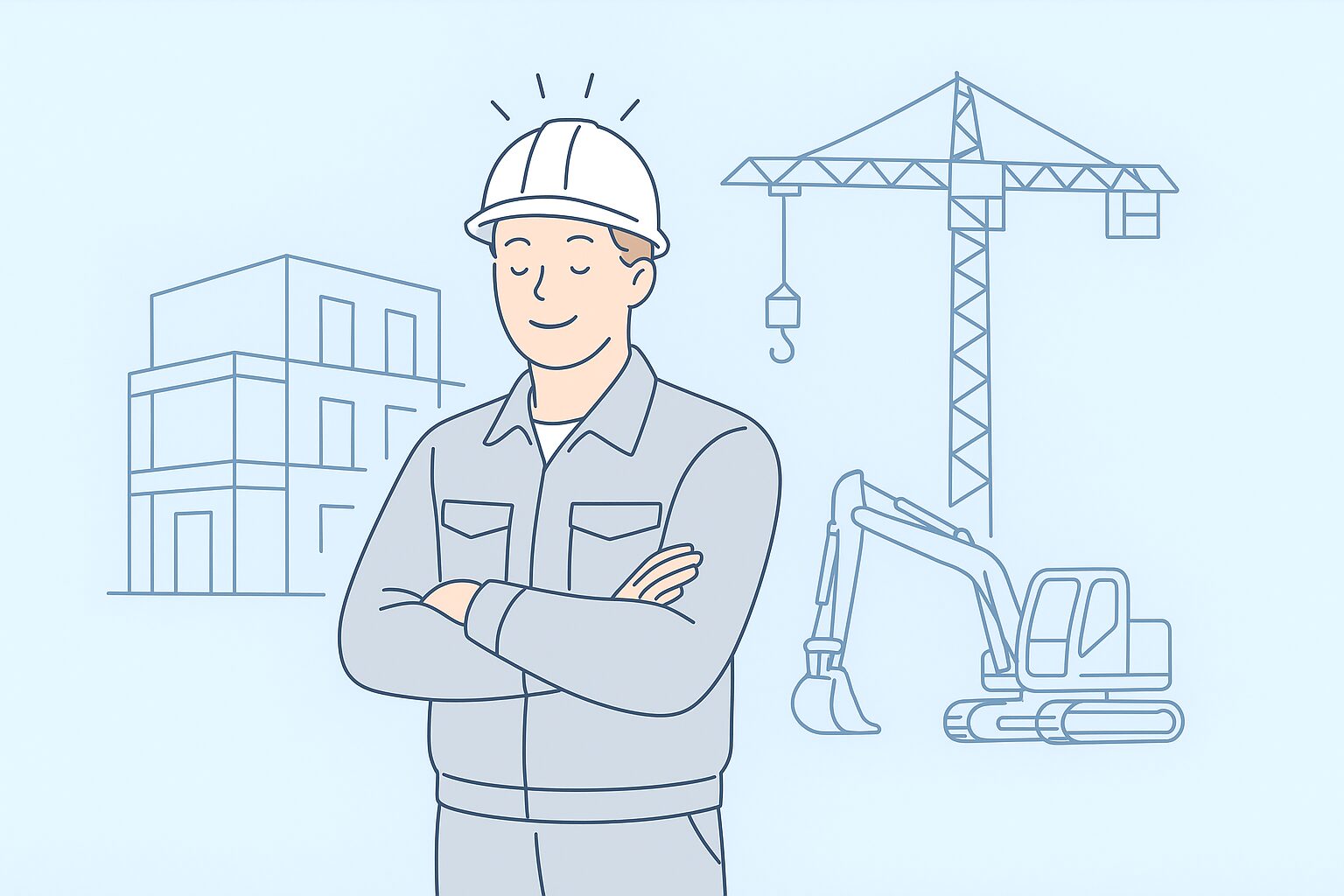
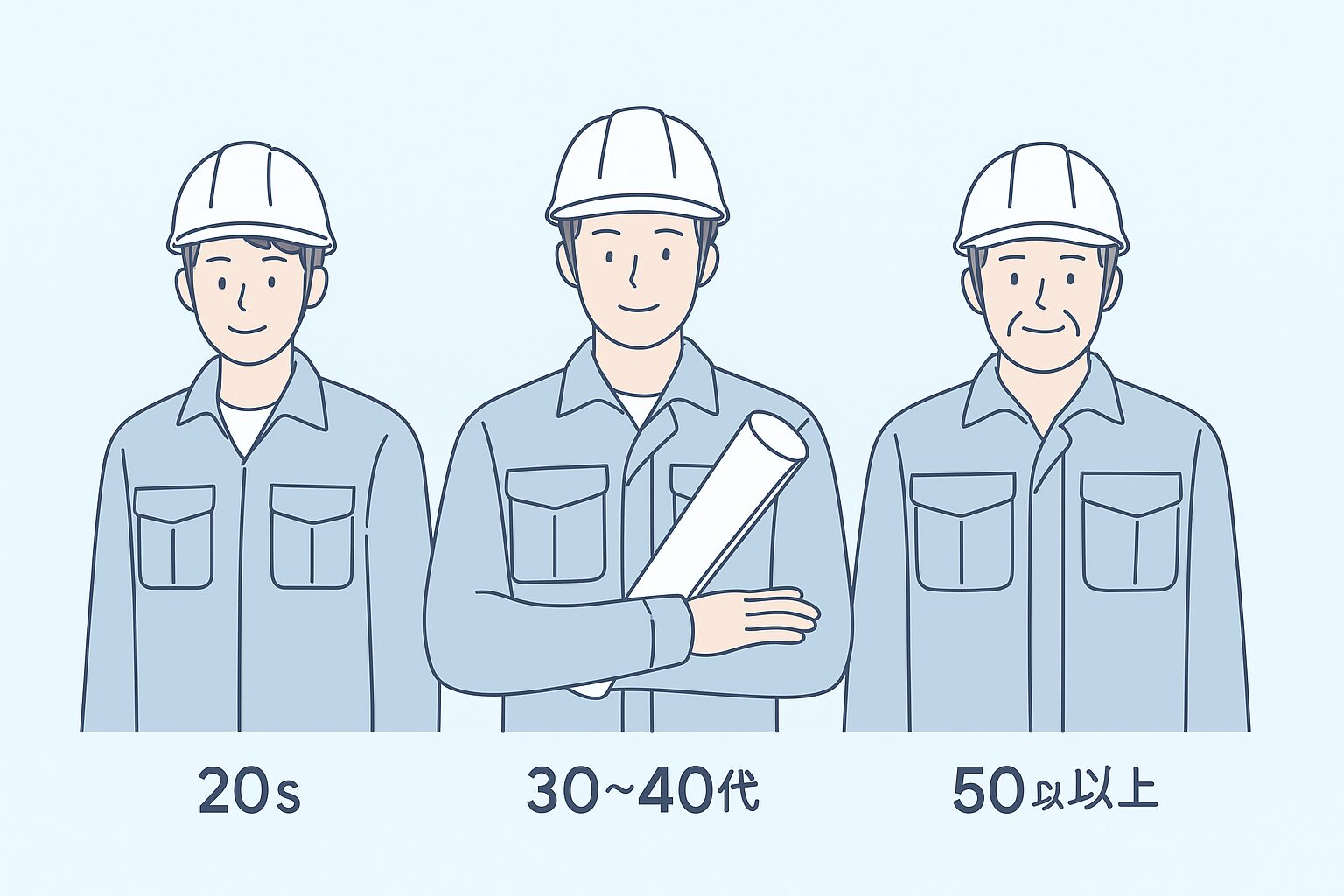




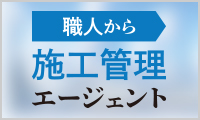








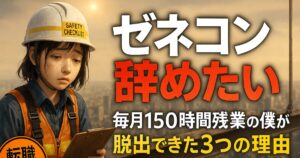
コメント