「職務経歴書 働いたことがない」と検索しているあなたは、
「職歴がない自分でも職務経歴書って必要なの?」「アルバイト経験を書いてもいいの?」
「何を書けば採用担当者に伝わるのか…」と、手が止まっていませんか。
新卒・既卒・フリーター・ニートなど、立場は違っても“書けることがない”という焦りや不安は共通しています。
しかし本当の悩みは、“書けないこと”そのものではなく、
“評価されるポイントがわからない”ことにあります。
経験が少なくても、伝え方次第で採用担当者に「意欲がある」「伸びしろがある」と感じてもらえる書き方があります。
私自身、建設業に10年務める中で、未経験者や職歴の浅い方の応募書類を多く見てきました。
その中で、「何をどう伝えるか」で印象が大きく変わることを実感しています。

この記事でわかること
- 新卒・既卒・中途それぞれの提出要否と狙い
- アルバイト経験や空白期間の扱いと書き方
- 採用担当者に伝わる構成とアピールポイント
- 省略しても支障がない要素と注意点
この記事では、職歴がない場合でも安心して書ける職務経歴書の基本構成や、
アルバイト・空白期間の扱い方、採用担当者が注目する“アピールの軸”を整理しています。
読み進めるうちに、「自分にも書ける内容がある」と自信を持って行動できるようになるはずです。
ぜひこの記事を参考に、あなたの一歩を形にしていきましょう。
迷ったときに見返せるよう、ブックマークしておくのもおすすめです。
働いたことがないのに職務経歴書は本当に必要?
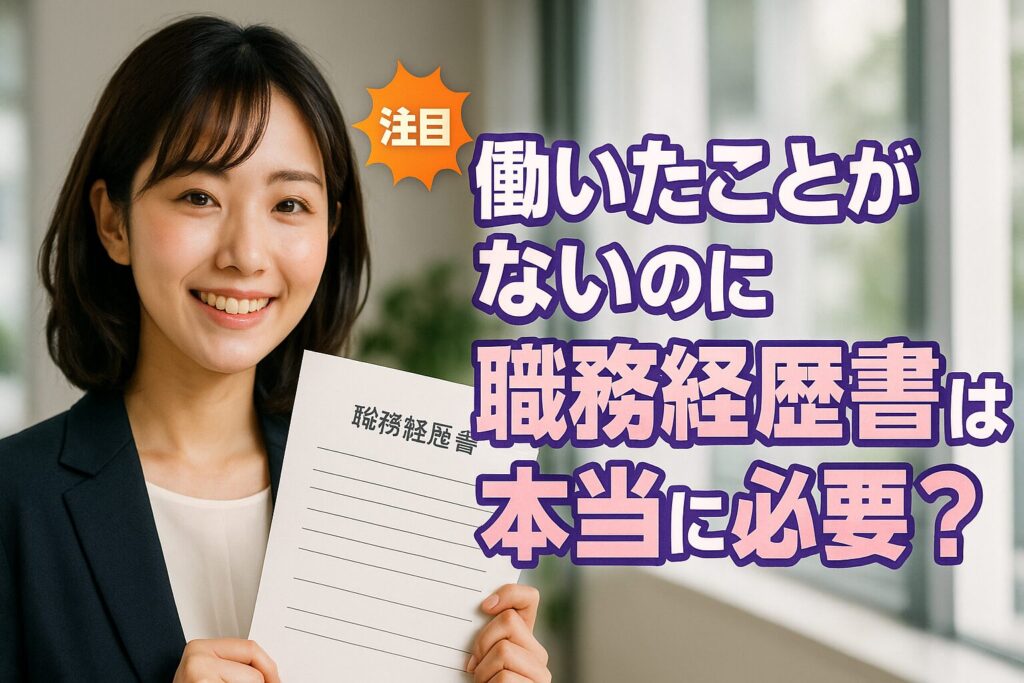
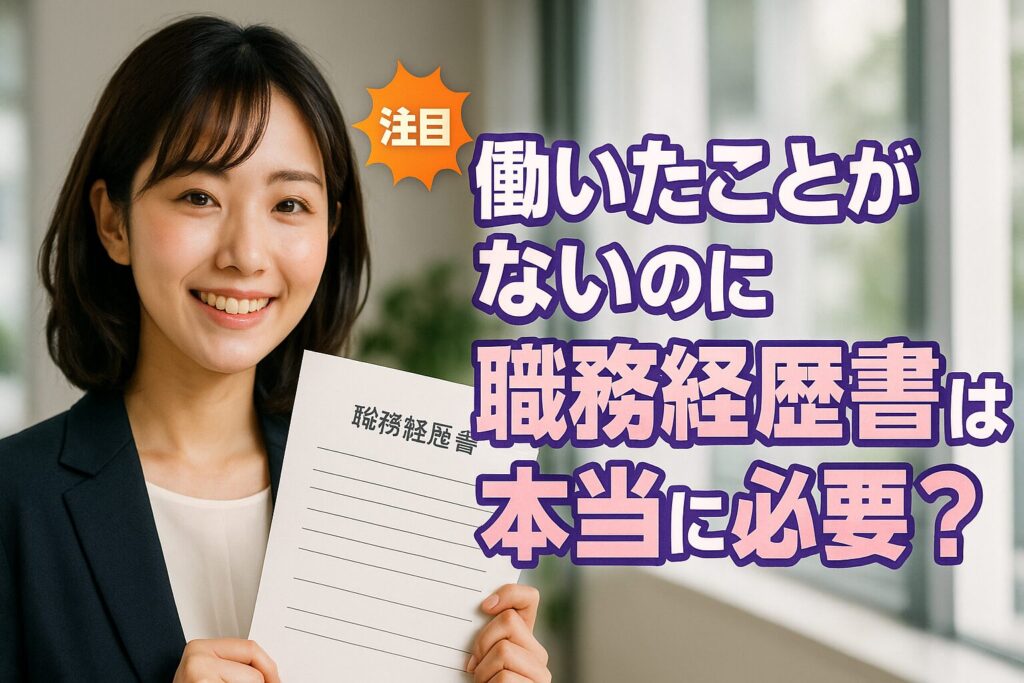



この章でわかること
- 新卒は職務経歴書が不要な理由とは?
- 既卒中途採用で職務経歴書が求められる背景
- アルバイト経験は職務経歴書に書いていいのか?
- 職歴なしでアルバイトなしの場合どうする?
- 何をアピールすれば採用担当者に響くのか?
新卒は職務経歴書が不要な理由とは?
新卒採用の多くは、教育課程を修了した時点での能力と将来性を評価する設計とされ、職務経歴書よりも履歴書やエントリーシート、学業・課外活動のポートフォリオが中心に用いられる運用が一般的です。企業側は、正社員としての職務遂行能力よりも、基礎学力、コミュニケーション、協働適性、コンプライアンス意識、将来的な伸長可能性といったポテンシャル面のシグナルを重視しがちで、これは日本固有の新卒一括採用慣行とも整合します。したがって、募集要項に明記がない限り、職務経歴書の提出は前提にならないことが多いと理解できます。
一方で、研究・制作実績が明確な領域(例:理工系研究、情報系プロジェクト、デザイン制作など)では、エビデンスの整理として簡易な職務経歴書相当の「活動サマリー」を求めるケースもあります。その場合、実務就労歴がなくても、活動名・役割・期間・成果指標・使用スキルの5要素を1〜3行で端的に記すだけで、読み手は評価の足場をつくれます。また、大学のキャリアセンターや公的支援(新卒応援ハローワーク等)では、新卒向けの提出書類テンプレートや相談窓口が整備されています。制度面の背景として、日本の雇用統計は就業・不就業を継続的に把握しており、若年層の雇用移行の実態は公的統計で確認できます(出典:総務省統計局 労働力調査)。
実務ポイント:新卒で職務経歴書の提出指示がある場合のみ、活動サマリー形式で最小限に。ない場合は履歴書・エントリーシート・ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を定量・定性の両面で補強し、課題→行動→成果→学びの順で整理すると評価者が読み解きやすくなります。
用語解説:ポテンシャル採用=実務経験の有無にかかわらず、将来的な成長可能性を主評価軸に置く採用方式。新卒では標準的な考え方です。
既卒中途採用で職務経歴書が求められる背景
既卒や中途採用は、職務の再現性(同様の環境で同等の成果を再度出せる見込み)を評価軸に据えるため、活動・経験・スキルを体系的に提示できる職務経歴書が求められやすい設計です。特に既卒で正規雇用の職歴が乏しい場合でも、学習・インターン・ボランティア・個人プロジェクト・アルバイトなどから、応募職務と論理的に接続できる素材を抽出し、職務要約に「適合性の仮説」を記すことが重要になります。採用担当者は、応募ポジションが要求する成果地図(KPI・KGI・職務要件)に照らして、応募者の経験断片を「どの工程・どのスキル群に結び付くのか」の視点で読み解きます。
そこで有効なのが、下記のような評価者視点のマッピングです。
| 評価観点 | 応募側が示す素材 | 読み手の判断材料 |
|---|---|---|
| 成果の再現性 | 達成値・改善率・担当範囲 | 環境差を埋めて同等の成果が出せるか |
| プロセスの質 | 課題把握→仮説→実行→検証 | 属人的でなく方法論として通用するか |
| 協働適性 | 関与者・役割定義・報連相 | チーム/顧客と摩擦なく進められるか |
| 学習/成長 | 新技能の習得・改善の痕跡 | オンボーディング後の伸長余地 |
既卒・中途で職歴が薄い場合は、成果値の不足をプロセスの質で補うのが定石です。たとえば販売職志望なら「来店客の需要探索→提案→クロージング」の各工程での工夫と結果を、事務職志望なら「正確性・期日遵守・改善提案」の履歴を記録し、IT志望なら「学習ロードマップ・制作物・Git等の管理」の痕跡で示す、といった具合です。なお、A4・1〜2枚に収めることが読み手負担の観点から推奨されます。分量を増やすほど評価が上がるわけではなく、応募職務との関連密度が鍵になります。
注意:汎用的なテンプレの流用は伝達効率が落ちる恐れがあります。求人票の職務要件・歓迎要件・選考フローを抜粋してから、経歴の対応関係を設計し、不要な要素は果断に省略しましょう。
アルバイト経験は職務経歴書に書いていいのか?
正社員経験がない状況では、アルバイト経験は書いていいとされています。評価の対象は「雇用形態」そのものではなく、職務関連性と成果の証跡です。たとえば小売アルバイトでも、在庫差異の是正、発注サイクルの改善、クレーム一次対応の標準化など、業務の本質に関わる改善があれば、応募職務に通じる力として評価可能です。大切なのは、単なる作業列挙ではなく、課題→行動→数値/事実→学びの順で提示することです。
読み手が判断しやすいよう、以下の翻訳例を参考にしてください。
| アルバイト経験の原文 | 職務関連性へ翻訳 |
|---|---|
| レジと品出しを担当 | ピーク時の待ち時間短縮を目的にレジ稼働率を見直し、平均待ち時間を約20%短縮(2.5分→2.0分) |
| 在庫管理を実施 | 棚卸し頻度と発注点の閾値設定を見直し、欠品率を月間2.1%→1.2%に低減 |
| 新人指導を担当 | 作業手順書を刷新しOJT時間を30%短縮、定着率を向上(1か月後の離職率を15%→8%) |
数値化が難しい場合は、頻度・規模・難易度などの事実で補強します(例:1日平均来客数、取扱SKU数、対応クレームの内訳など)。指標の粒度は完璧である必要はなく、相対的な変化が示せれば十分に読み手の判断材料になります。さらに、応募先との関連づけを忘れずに行いましょう。営業志望なら「提案件数・受注率・客単価」、事務志望なら「処理件数・エラー率・締切遵守」、接客志望なら「CS指標・リピート率・推奨指標」など、職種のKPI語彙へ翻訳して記すと伝達効率が上がります。
注意:職務と無関係な武勇伝や過度な私情は逆効果になり得ます。職務遂行に資する事実だけを厳選し、数値・役割・手順で客観化しましょう。
職歴なしでアルバイトなしの場合どうする?
職歴もアルバイト経験もない場合、評価材料が「空白」に見えることへの不安を抱きがちです。しかし実際の採用現場では、ブランク期間の内容そのものよりも、「その期間をどのように過ごし、何を学び、今後どう活かすか」を読み取っています。したがって、焦点を“職歴”から“活動内容と学習姿勢”に移すことが極めて重要です。
例えば、家事や介護、病気療養、資格勉強、オンライン学習、ボランティア、創作活動、家業の手伝いなども十分に評価の対象となり得ます。これらは一見「就労」ではなくても、時間管理、コミュニケーション、継続力といった汎用スキル(いわゆるソフトスキル)を磨く場として解釈可能です。職務経歴書に書ける活動は、雇用契約の有無ではなく、学びや成長の可視化で判断するという視点を持つと、記載できる素材が格段に増えます。
記述のポイントは、①期間、②目的、③行動内容、④得たスキル・成果の4点を簡潔に示すことです。例えば「2023年4月〜2024年3月:家族の介護を行いながら、時間管理や報告スキルを意識的に改善。介護職員初任者研修を修了。」のように書くと、行動と学習の両面を伝えられます。
記載例:
2023年4月〜2024年3月 家族の介護のため就業に至らず。介護に関する基礎知識の学習とPCスキルの習得に注力。
使用教材:介護職員初任者研修、MOS Excel講座(独学)。
さらに、空白期間の説明では「現状の意欲」を明確に添えることが評価を補完します。たとえば「現在は事務職として再スタートを目指し、Word・Excelの資格取得に向けて学習中」など、今後の方向性を加えることで、受け手は前向きな印象を受けます。採用担当者は「過去」よりも「これから」何をする人かを見ているため、空白期間の表現を恐れず、誠実かつ具体的にまとめましょう。
公的支援機関でも、ブランク期間のある求職者を対象とした書類作成支援が整備されています。たとえば、厚生労働省が運営するハローワークでは、未就労期間の整理方法や履歴書・職務経歴書の記載支援を受けられます(出典:厚生労働省 ハローワーク)。
ポイント:空白期間はマイナス評価ではなく、学びと成長を示す素材。期間・内容・得たスキル・今後の志向を明記し、「何もしていない」印象を払拭しましょう。
何をアピールすれば採用担当者に響くのか?
採用担当者は、応募者の経歴の量ではなく「再現性」「貢献度」「学習意欲」を見ています。働いたことがない場合でも、これらの要素を職務経歴書で具体的に可視化すれば、十分に評価の対象となります。重要なのは、実績の大小ではなく、成果を導く思考や行動プロセスをどう伝えるかです。
アピール内容を整理する際は、次の3ステップを意識してください。
チェックポイント
- 課題発見:どんな問題や目標を見つけ、どう捉えたか。
- 行動と工夫:課題に対してどんな行動を取り、どんな改善を試みたか。
- 結果と学び:その結果、何を得たのか。今後どのように活かせるのか。
たとえば、家事や介護経験を通して得た「段取り力」や「優先順位付け」、趣味の制作活動で培った「問題解決力」や「集中力」も、転用可能スキル(Transferable Skills)として扱えます。職務経歴書では、こうしたスキルを業務の文脈に落とし込み、「この能力が御社の〇〇職においてどのように活きるか」を明示することで、説得力を高められます。
また、採用担当者が目を通す時間は平均1〜2分と短いため、最初の職務要約(リード文)で最も伝えたい強みを打ち出すのが有効です。そこでは、「問題を発見し、粘り強く改善した経験」や「目的達成に向けた具体的な努力」を簡潔にまとめると良いでしょう。読み手に「この人は成長できそうだ」と思わせる一文を冒頭に置くことが、書類選考通過の鍵です。
おすすめ構成:
【課題】→【行動】→【成果】→【学び】→【転用可能スキル】の順に整理。
この流れは新卒・既卒・中途・フリーター問わず効果的で、再現性の高い自己PRが可能です。
さらに、データ的な裏付けとして、採用担当者の関心は「人柄」よりも「スキル・姿勢・柔軟性」にシフトしている傾向があります。リクルートワークス研究所による調査でも、2023年度以降は中途採用基準の約60%がスキル重視で構成されていると報告されています(出典:リクルートワークス研究所「Works調査レポート」)。この流れを踏まえれば、働いたことがなくても、学び続ける姿勢を定量的に示すことが最も有効な戦略と言えるでしょう。
職務経歴書働いたことがない人の書き方ガイド
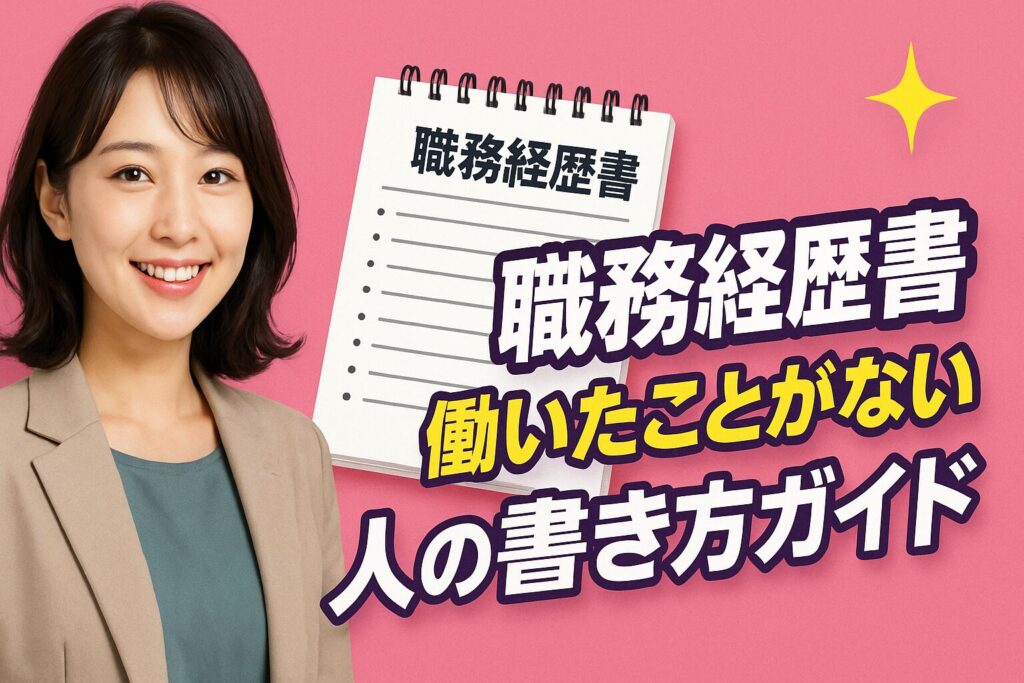
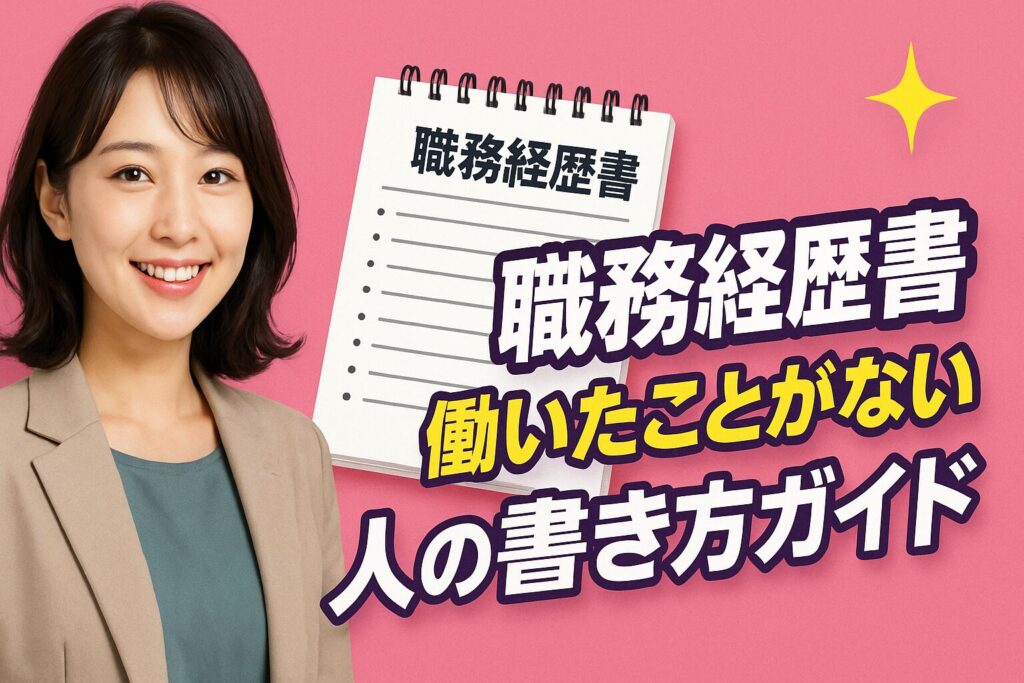



この章でわかること
- ない場合の書き方で注意すべきポイント
- ニートで職務経歴書を出す際の工夫とは?
- フリーターで職務経歴書を作るときの秘訣
- 好印象を与える書き方のコツを押さえよう
- 省略してもいい項目とその判断基準
- 職務経歴書働いたことがない人が最後に意識すべきこと
ない場合の書き方で注意すべきポイント
職歴がない場合でも、職務経歴書は単に「空欄で提出」してよいわけではありません。採用担当者は、その書類を通して「応募者の情報整理能力」「論理的思考」「社会人としての姿勢」を判断します。したがって、未就労であっても書式を整えたうえで、活動・学習・スキル習得・目的意識の4点を軸に記述することが肝要です。
一般的な構成は以下の通りです。
① 職務要約:自分の強みや志向、学習の方向性を100〜200文字程度で記す。
② 活動概要:学業・ボランティア・アルバイト・個人制作などを時系列に整理。
③ 活かせるスキル:応募職種との関連性が高いスキルや資格、知識を列挙。
④ 自己PR:成果・姿勢・将来のビジョンを一文で結ぶ。
記載内容は多くなくても、論理的に構成されたフォーマットであることが評価対象となります。採用担当者に「この人は整理して伝える力がある」と思わせるだけでもプラス評価に転じます。
さらに、「ない」ことを恐れず、「何を準備したか」を書くことがポイントです。資格勉強、ポートフォリオ作成、就職セミナーへの参加など、行動の証跡を提示しましょう。厚生労働省の調査によると、求職活動を「継続的に行っている」若年層の就業率は、非活動層に比べて約1.8倍高い傾向が示されています(出典:厚生労働省「若年者雇用実態調査」)。つまり、「準備している姿勢」を可視化するだけでも、就職成功率は確実に上がるのです。
まとめ:「ない場合の書き方」は、「何をやってきたか」ではなく、「どんな準備と成長をしているか」を明確に書く。具体的なスキルや学びを通じて、将来性を感じさせる構成を意識しましょう。
ニートで職務経歴書を出す際の工夫とは?
ニート(就業経験がない、または就業を離れている期間がある状態)で職務経歴書を提出する場合、多くの人が「書けることがない」と悩みます。しかし、採用担当者はブランクそのものを問題視しているわけではありません。注目しているのは、「その期間に何を学び、どう行動してきたか」、そして「今後どう働こうとしているのか」という前向きな意志です。
ニート期間を記載する際の最も重要な考え方は、「空白の説明」ではなく「学習と行動の記録」を書くことです。たとえば、生活リズムの立て直しや資格学習、ボランティア参加、家族の介護、創作活動なども立派な“行動実績”として職務経歴書に記載できます。
ニート期間の記載における基本構成
① 期間:2022年4月〜2023年9月
② 状況:就職活動準備・生活改善のための期間
③ 活動内容:資格取得の学習、職業訓練受講、日常生活の安定化
④ 得たスキル:時間管理力、自己分析力、目標設定力
このように「事実を淡々と」「前向きな学びを強調する」記述が基本です。感情的な言い訳や理由の羅列は避け、できるだけ中立的な文体で書きましょう。
また、ニート期間における職業訓練やセミナー参加、ハローワークの支援利用は、高い評価につながります。これらの活動は、自己改善への意欲と社会復帰への主体性を証明する材料になるためです。厚生労働省の能力開発基本調査によると、職業訓練や資格学習を受けた人の約72%が半年以内に就業機会を得たと報告されています。数字の裏付けを意識して記載すると、説得力が増します。
ポイント:ニート期間は「自分を見直し、再スタートのために準備した時間」として扱う。活動内容を具体的に書くことで、評価者に「成長意欲のある人」と印象づけることが可能です。
フリーターで職務経歴書を作るときの秘訣
フリーターとして複数のアルバイトを経験している場合、職務経歴書では「バラバラな経歴」に見せるのではなく、「一貫した成長の流れ」としてまとめることが鍵です。雇用形態にかかわらず、担当した業務を職種ベースで整理し、応募先に関連するスキルを中心に据えて書きましょう。
例えば、飲食店・販売・事務補助など異なる業務を経験していても、共通して「顧客対応」「在庫管理」「チーム連携」などが身についていれば、それを軸にストーリーを構築できます。このような整理は、採用担当者に「目的を持って働いてきた」印象を与え、即戦力としての期待を高めます。
書き分けの具体例
| 職種 | アピールポイント | 職務経歴書での書き方例 |
|---|---|---|
| 飲食接客 | 臨機応変な対応・顧客満足の向上 | 1日平均150名の来客対応に従事し、顧客満足度アンケートで平均4.7点を維持。 |
| 販売 | 数字で成果を示す提案力 | 店舗の月間売上目標120%を達成し、顧客リピート率を15%向上。 |
| 事務補助 | 正確性と効率性 | データ入力ミスを3ヶ月で半減させる業務改善を提案し採用。 |
フリーター経験をプラスに転換するコツは、業務内容を「成果と数字」で補強することです。短期バイトが多くても、「短期間で成果を出す柔軟性」や「異なる職場での適応力」として表現できます。逆に、すべてを網羅しすぎると焦点がぼやけるため、応募職種と関係の深い経験だけを選びましょう。
ヒント:応募先が求めるスキルに合わせて経歴を「再構成」する。たとえ非正規でも、プロセス・結果・改善の工夫を明確にすれば、正社員経験に近い説得力を持たせられます。
好印象を与える書き方のコツを押さえよう
職務経歴書の印象を左右するのは「内容」だけでなく、「読みやすさ」と「論理構成」です。採用担当者は数十人分の書類を短時間で読むため、視認性の高い構成と自然な流れが好印象の決め手になります。
見やすさ・読みやすさの3原則
- 見出しを使って構造化する:セクションを分けて段落を整理。
- 一文を短く保つ:50〜70文字以内で簡潔に要点をまとめる。
- 数字と具体例を入れる:「努力しました」ではなく「〇〇%改善」「〇件対応」のように定量化。
また、文体はです・ます調で統一し、過去の行動には過去形を、意欲や今後の展望には現在形を使うと読みやすくなります。これはビジネス文書の基本でもあり、細部の統一が全体の印象を引き締めます。
さらに、採用現場で高評価を得やすい書き方の特徴として、「自分視点ではなく、相手視点で書かれている」ことが挙げられます。「自分が成長した」ではなく「職場にどう貢献したか」「顧客にどう価値を与えたか」を中心に語ると、説得力が格段に上がります。
チェックポイント文末表現を確認しよう。
- ×:〜しましたが、〜でした。
- ○:〜に取り組み、〜を達成しました。
- 前向きな接続語(「結果」「そのため」「具体的には」など)で流れを作ると、より好印象になります。
厚生労働省の採用調査では、企業が履歴書・職務経歴書から重視する項目の上位に「文章の構成力」「論理性」「誤字脱字の有無」が挙げられています(出典:厚生労働省「雇用動向調査」)。つまり、文章の書き方そのものが、社会人基礎力の評価に直結しているのです。
省略してもいい項目とその判断基準
働いた経験がない場合、職務経歴書の内容を「どこまで書くべきか」という点に悩む方は多いです。採用担当者に伝えるべき情報と、省略しても評価に影響しない情報を峻別することが、読みやすく効果的な職務経歴書を作成する第一歩となります。
まず大前提として、職務経歴書の目的は「応募先が求める人材要件に対して、自分がどのように貢献できるかを伝える資料」であるという点です。したがって、その目的に関係しない情報は、どれほど努力して書いても採用担当者の判断に寄与しないことが多いのです。書きすぎによって焦点がぼやけるよりも、必要最小限に絞り、構成の明瞭さを優先しましょう。
以下に、省略可能な要素と必須要素の目安をまとめます。
| 項目 | 省略の可否 | 備考・判断基準 |
|---|---|---|
| 住所(都道府県以外) | 省略可 | 個人情報保護の観点から詳細住所は不要。市区町村までで十分。 |
| 電話番号・メールアドレス | 必須 | 応募者連絡の根幹。正確性を最優先。 |
| 生年月日 | 募集要項で指示がなければ省略可 | 履歴書に記載済みであれば、重複を避ける。 |
| 職務経歴がない期間の詳細 | 部分省略可 | 目的に関係しない詳細(個人事情など)は書かない。 |
| 学生時代の細かい活動 | 省略可 | 成果や学びが職務に関連しない場合は削除。 |
| 趣味・特技 | 省略可 | 職務適性に関係しない場合は履歴書のみに記載。 |
| 古い活動(5年以上前) | 省略可 | 職務に直結する場合のみ残す。 |
特に、未就業者や既卒・フリーターの方の場合は、「応募職種と関係する内容」だけを抽出する意識が重要です。履歴書と職務経歴書が重複しすぎると冗長になり、採用担当者の興味を削ぐ可能性があります。逆に、応募先の仕事内容と明確にリンクするスキル・経験・学習内容は、詳細に記載して構いません。
また、ファイル形式やテンプレートの指定には必ず従いましょう。多くの企業では、WordまたはPDF形式が指定されています。提出形式を誤るだけで「指示を理解していない」と判断される場合もあります。さらに、書式崩れやレイアウトの乱れを防ぐため、最終的にPDF化して提出するのが一般的です。
注意:募集要項の中には、「写真付き」「署名あり」「職務経歴書不要」といった明示的な指示がある場合があります。応募先が定めるフォーマットを最優先し、テンプレートを独自変更する際は慎重に。公的な形式遵守は信頼性を高める要素の一つです。
なお、厚生労働省の職業紹介事業報告書によれば、応募書類の不備や記載漏れを理由に選考対象外となるケースは全体の約12%を占めています。形式的な部分を軽視せず、提出前に必ず以下の3点を確認してください。
チェックポイント
- 指定フォーマット・ファイル形式に合致しているか
- 誤字脱字・表記ゆれ(西暦/和暦など)がないか
- 日付・署名・連絡先が最新であるか
つまり、内容面の充実以上に「書類としての正確性・整合性」を保つことが、信頼獲得の第一歩なのです。
職務経歴書働いたことがない人が最後に意識すべきこと
職務経歴書を「働いたことがない状態」で作成することは、最初は難しく感じられるかもしれません。しかし、評価の基準を知り、構成を整えれば、誰でも採用担当者の目に留まる書類を作ることができます。最後に、本記事で扱った要点を実務的な観点から再整理しましょう。



この記事のまとめ
- 新卒は募集要項に従い、基本は履歴書中心で進める。
- 既卒は活動実績や学習履歴を整理して職務要約で先に示す。
- 中途は実績・スキルを軸に経歴を構造化し、成果指標を入れる。
- アルバイト経験は応募職種との関連性を強調して書く。
- 空白期間は「理由+学び+今後の意欲」で説明する。
- 短期・単発の仕事は概要のみに留め、冗長化を避ける。
- 一文を短く、能動的な表現(〜を実施し、〜を達成)を使う。
- 数値・頻度・成果指標で再現性を可視化する。
- 提出形式(PDF/Word)・テンプレート指示を厳格に順守する。
- 誤字脱字、フォント不統一、日付表記のズレを必ず最終確認。
働いた経験がない人にとっての職務経歴書は、過去の経歴を示す書類というより、「成長意欲と今後の可能性」を証明する自己分析レポートに近いものです。採用担当者は“完璧な経歴”を期待しているわけではなく、“成長の兆し”を探しています。そのため、学び・挑戦・行動の履歴を具体的に言語化することが、最大のアピールになります。
結論:経歴がないことを恐れず、「これまで」と「これから」を一貫したストーリーでつなぐ。あなたの歩みを言葉で整理することが、最も誠実で効果的な職務経歴書の書き方です。
参考・出典(公的・一次情報源)
・新卒採用に関する労働統計—総務省統計局「労働力調査」
・職業訓練と再就職状況—厚生労働省「能力開発基本調査」
・応募書類の不備に関する統計—厚生労働省「職業紹介事業報告書」
・採用における文章力評価の重要性—厚生労働省「雇用動向調査」
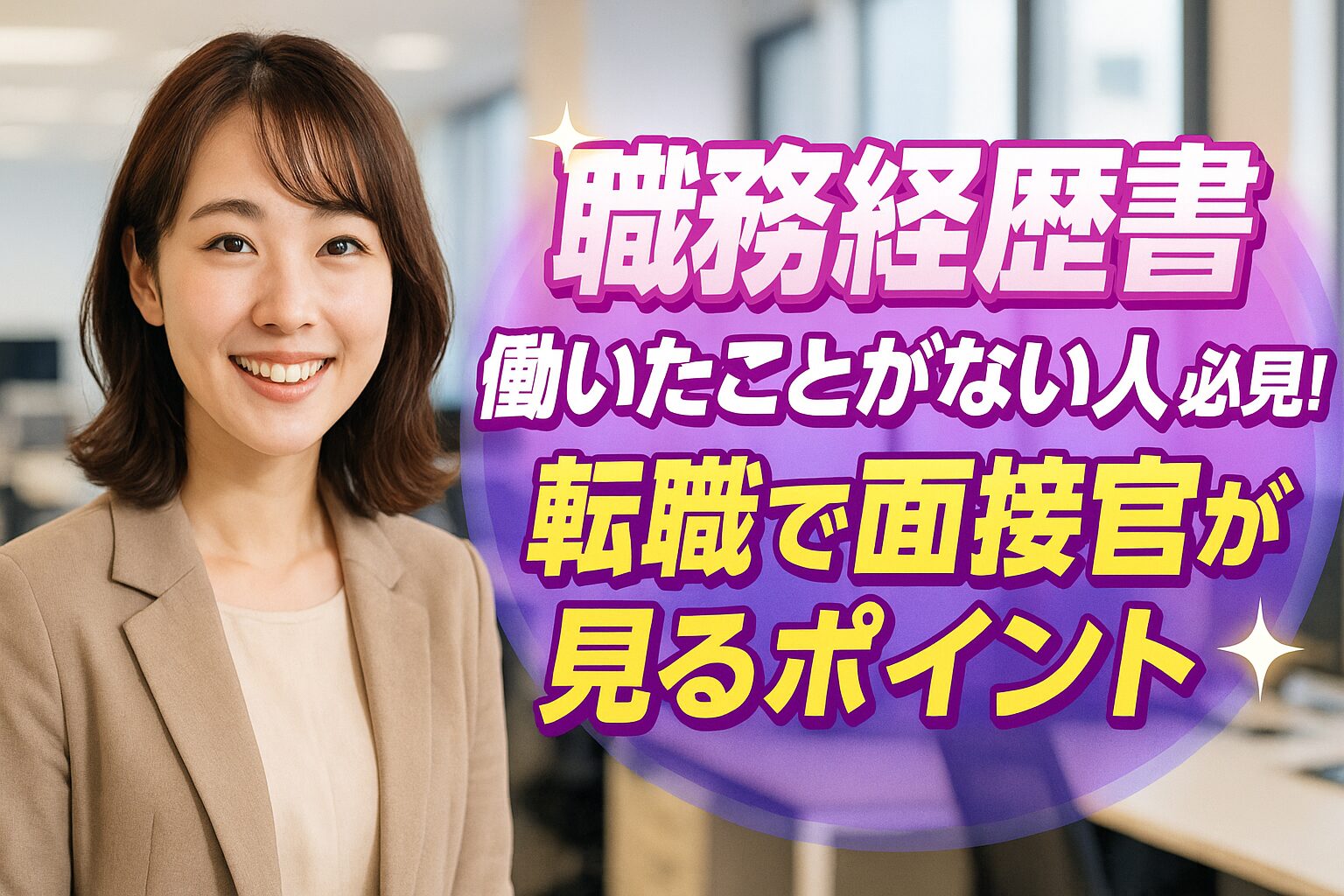












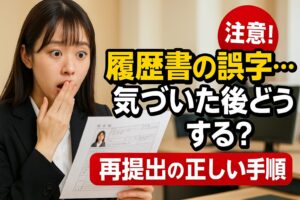
コメント