「1級土木施工管理技士の試験、合格率は厳しいって聞くけど実際はどうなんだろう…」
建設業界でのキャリアアップを目指す方なら、こんな疑問を持ったことがあるのではないでしょうか。
一級土木施工管理技士は難関資格として知られていますが、その実態は年によって変動があり、正確な情報を知ることが合格への第一歩となります。
特に2024年度は受験資格の緩和により受験者数が急増し、一次検定の合格率は44.4%まで下がりました。二次検定もさらに厳しく、例年30%台の合格率で推移しています。
これらの数字を見ると不安になるかもしれませんが、しっかりとした対策と準備があれば、十分に突破することが可能です。
この記事では、最新の合格率データをもとに、合格するための効果的な勉強法や資格取得後の年収アップの可能性まで、一級土木施工管理技士を目指す方に必要な情報を徹底解説します。
難易度の高い資格だからこそ、正しい知識と戦略で挑むことが大切です。
あなたの土木キャリアを大きく前進させる一級土木施工管理技士。その合格への道のりを、共に歩んでいきましょう。
読みたいところへジャンプできるよ!
こんな悩みを解決する記事を用意しました!
もしも転職をお考えなら・・・
「いきなり転職するのは不安…」と感じる方も、面談だけならリスクゼロ!
まずは話を聞いてみることから始めてみてください。
✅ 今すぐ【Re就活エージェント】の詳細を見る
1級土木施工管理技士合格率は低い?最新データで解説!
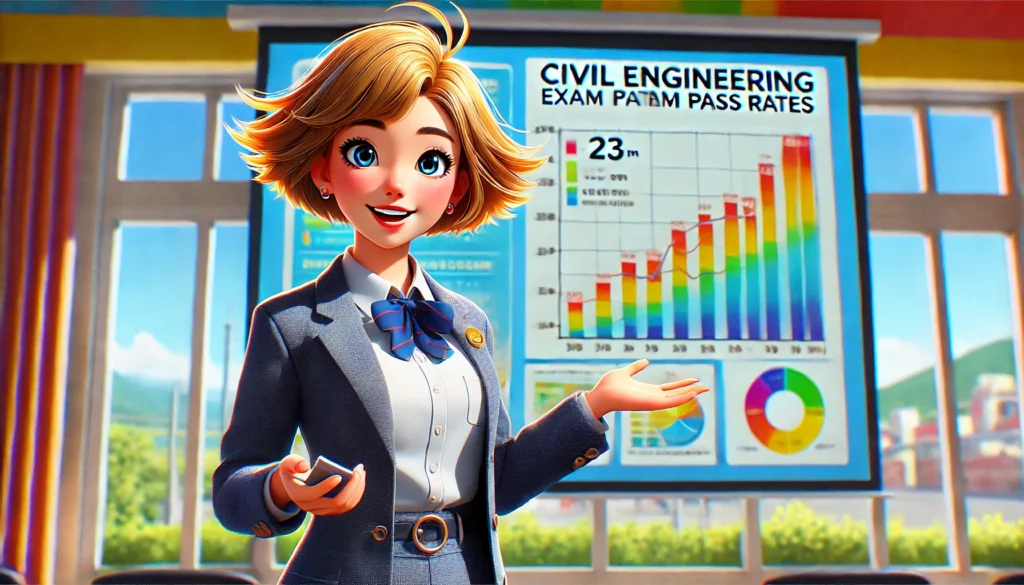
- 合格率過去データから見える難関の実態!
- 土木施工管理技士1級は何割で合格できる?
- 合格発表はいつ?見逃せないチェックポイント!
- 合格基準が変更?新制度の影響を徹底解説!
- 他の資格と比較してどれだけ難しいのか?
合格率過去データから見える難関の実態!

| 年度 | 一次検定合格率 | 二次検定合格率 |
|---|---|---|
| 2021年度 | 60.6% | 36.6% |
| 2022年度 | 54.6% | 28.7% |
| 2024年度 | 44.4% | 41.2% |
1級土木施工管理技士の合格率は、年によって多少の上下はあるものの、全体的に見ると一定の傾向があります。特に注目すべきは、一次検定と二次検定で難易度に大きな差があることです。
一次検定(旧・学科試験)は、比較的合格率が高く、例年50〜60%前後で推移しています。
例えば、2021年度は60.6%、2022年度は54.6%と、半数以上の受験者が合格していることがわかります。
ただし、2024年度は受験資格の緩和により受検者数が急増した影響もあってか、合格率が44.4%に下がりました。
一方で、二次検定(旧・実地試験)は、合格率が30%台にとどまることが多く、2022年度に至っては28.7%とかなり厳しい結果となっています。
つまり、一次は突破できても、二次の壁が高いという構造になっているのです。
このようなデータを見て、「思ったより合格率が低い…」と不安になるかもしれません。
でも、数字の背景を理解することで、必要な対策が見えてきますよ。
大切なのは、過去の合格率をただ見るのではなく、自分が合格するために何が必要かを考えることです。
数字は冷静に、でも前向きに受け止めてくださいね。
土木施工管理技士1級は何割で合格できる?

1級土木施工管理技士の合格基準は、基本的に「60%以上の正答率」が求められます。つまり、試験問題のおおよそ6割を正確に解ければ合格ラインに到達すると考えてよいでしょう。
ただし、これはあくまで最低ラインです。問題の難易度や出題傾向によって、実際の合格者の正答率はそれ以上であることも少なくありません。
特に注意が必要なのは、二次検定です。
一次と違い、マークシートではなく記述式で、自身の実務経験をもとに論述しなければなりません。
「6割取れば合格」と言っても、採点基準がやや曖昧な部分もあり、記述内容の論理性や表現力、専門知識の正確さが問われます。
ですので、「何割取ればいいか?」という考えにとらわれ過ぎるよりも、「どのようにして確実な得点を積み重ねるか?」を意識して学習を進めた方が結果的に合格に近づきますよ。
また、得点配分にも注意が必要です。重要な記述問題で点を落とすと、全体の得点にも大きく影響します。つまり、バランス良く、かつ確実に得点できる力をつけることが合格へのカギになります。
一次検定(択一式マークシート形式)
一次検定は幅広い知識が求められる択一式試験で、全体の正答率60%以上で合格となります。出題範囲は「土木工学」「法規」「施工管理法」など多岐にわたりますが、効率的に学習するために優先度を分けます。
| 優先度 | 科目 | 理由 |
|---|---|---|
| 優先すべき科目 | 施工管理法 | 応用能力が問われる問題が多く、近年の試験で重視されている。得点源にしやすい。 |
| 土木工学(基礎・専門) | 出題数が多く、基本的な知識が問われるため、基礎固めが重要。 | |
| 法規 | 建設業法や関連法令の問題が出題され、暗記で対応可能な部分が多い。 | |
| 後回しにしてもよい科目 | 共通工学 | 出題範囲が広く、専門性が高いが、得点への影響が比較的小さい。 |
| 建設副産物・環境保全 | 出題頻度が低く、配点が小さい傾向にある。 |
二次検定(記述式)
二次検定は記述式で、施工経験記述が特に重要です。
総出題数は11問(必須3問、選択8問中4問解答)で、制限時間は2時間45分とタイトです。
施工経験記述が無記載だと採点されないため、まずこれを最優先に準備する必要があります。
| 優先度 | 科目 | 理由 |
|---|---|---|
| 優先すべき科目 | 施工経験記述 | 必須問題であり、無記載だと失格。事前に経験を整理し、添削を受けるべき。 |
| 工程管理、安全管理 | 頻出テーマで、毎年いずれかが出題される。実務経験を活かしやすい。 | |
| 品質管理、出来形管理 | 施工管理の基本であり、出題可能性が高い。記述対策が重要。 | |
| 後回しにしてもよい科目 | 建設副産物・環境保全 | 出題頻度が低く、選択問題の中で優先度が低い。 |
| 土工、コンクリート工 | 選択問題として出題されるが、難易度が高く、得意でない場合は後回し可。 |
補足と学習のポイント
- 一次検定では、施工管理法や土木工学の基礎知識を優先的に固めることで、効率的に得点を積み上げられます。法規は暗記で対応できるので、早めに取り組むと良いでしょう。一方、共通工学や環境保全は出題頻度が低いため、基礎的な理解にとどめておけば十分です。
- 二次検定では、施工経験記述が合否を左右する最重要科目です。事前に自分の経験を整理し、テーマ(工程管理、品質管理など)に沿った記述を準備することが必須です。また、選択問題では難易度の高い問題(例: 土工やコンクリート工)が出る場合があるので、得意分野を優先して解答する戦略が有効です。
あなたの努力が6割を超える力を自然に育ててくれるはずです。焦らず、ひとつずつ積み重ねていきましょうね。
合格発表はいつ?見逃せないチェックポイント!

試験が終わった後、気になるのはやはり「合格発表はいつ?」ということですよね。合格発表のタイミングを把握しておくことで、次のステップにもスムーズに進むことができます。
1級土木施工管理技士の合格発表は、例年、一次検定が8月中旬ごろ、二次検定は12月中旬ごろに行われます。試験から発表まで少し期間がありますが、その間は気を抜かず、必要であれば次回の対策に向けて準備を始めるのもおすすめです。
合格発表の確認方法はとても簡単です。まずは「一般財団法人 全国建設研修センター」の公式サイトにアクセスしてください。発表当日には特設ページが設けられ、受験番号を入力することで合否が確認できます。
また、通知書も郵送されるので、そちらでも結果を確認できます。
ただ、万が一の郵送遅延などを考えると、まずはウェブで確認するのが安心ですね。
注意点としては、受験番号を控えておくこと。試験から日数が空くと、うっかり紛失してしまうこともあるので、スマホなどにメモしておくとよいでしょう。
合格発表の日は、あなたの努力が報われる大切な瞬間です。できるだけ余裕を持って準備し、落ち着いて結果を迎えてくださいね。
合格基準が変更?新制度の影響を徹底解説!
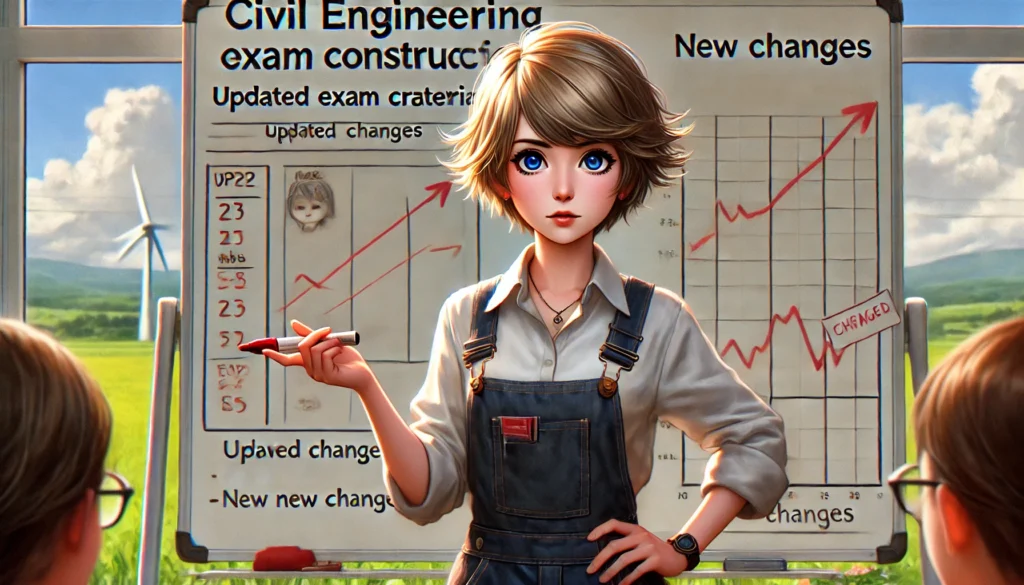
1級土木施工管理技士の試験制度は、令和6年度から大きな変更が加えられました。
この変更は、これまでの受験者にとっても、これから受けようと考えているあなたにとっても、しっかりと把握しておくべき重要なポイントです。
今回の見直しで、これまで「学科試験」「実地試験」と呼ばれていたものが、それぞれ「第一次検定」「第二次検定」という名称に変わりました。
ただ名前が変わっただけではありません。中でも注目すべきは、第一次検定の受験資格が大幅に緩和されたことです。
従来は、一定の実務経験がなければ受験すらできませんでしたが、令和6年度以降は「19歳以上」であれば誰でもチャレンジ可能になりました。この変更により、若い世代の受験者が一気に増えたことも特徴ですね。
ただし、この受験資格の緩和は、一方で合格率の低下という影響ももたらしました。受験者数が増えた分、試験の競争は激しくなり、令和6年度の一次試験合格率は44.4%と、過去10年で最も低い水準となりました。
これには少し驚いたかもしれませんね。でも、だからこそ正しい情報をもとに、きちんと対策を立てることが大切になりますよ。
変更によってチャレンジしやすくなった反面、合格までの道のりは一層しっかりと準備して臨む必要があります。情報のアップデートを忘れず、あなたに合った学習計画を立てていきましょうね。
他の資格と比較してどれだけ難しいのか?

1級土木施工管理技士の難しさについて、「他の建設系資格と比べてどうなの?」と気になる方は多いのではないでしょうか。実際に、業界には数多くの関連資格があり、その中で1級がどの位置づけなのかを知ることは大切です。
結論から言うと、1級土木施工管理技士は、非常に難易度の高い国家資格です。他の施工管理技士や技術系資格と比較しても、学ぶべき知識の範囲が広く、実務経験も問われるため、簡単に取得できるものではありません。
例えば、2級土木施工管理技士は、合格率が比較的高く、実務経験が浅い方でも合格できるチャンスがあります。一方、1級は二次試験での記述問題が非常に難解であり、実際の現場経験を元にした論述力が求められます。
また、電気工事施工管理技士や建築施工管理技士などと比べても、土木分野は取り扱う工事の種類が多岐にわたり、知識の深さと広さが両方必要になります。
このため、資格の取得には計画的な学習と、実務を通じた理解の深まりが不可欠になります。ですが、それだけに取得できたときの価値や信頼性は非常に高く、企業からも重宝される存在になれますよ。
難しいからこそ、取得後のキャリアや待遇に直結しやすい。それが1級土木施工管理技士という資格の大きな魅力なんですね。
1級土木施工管理技士合格率から見る攻略法とは?
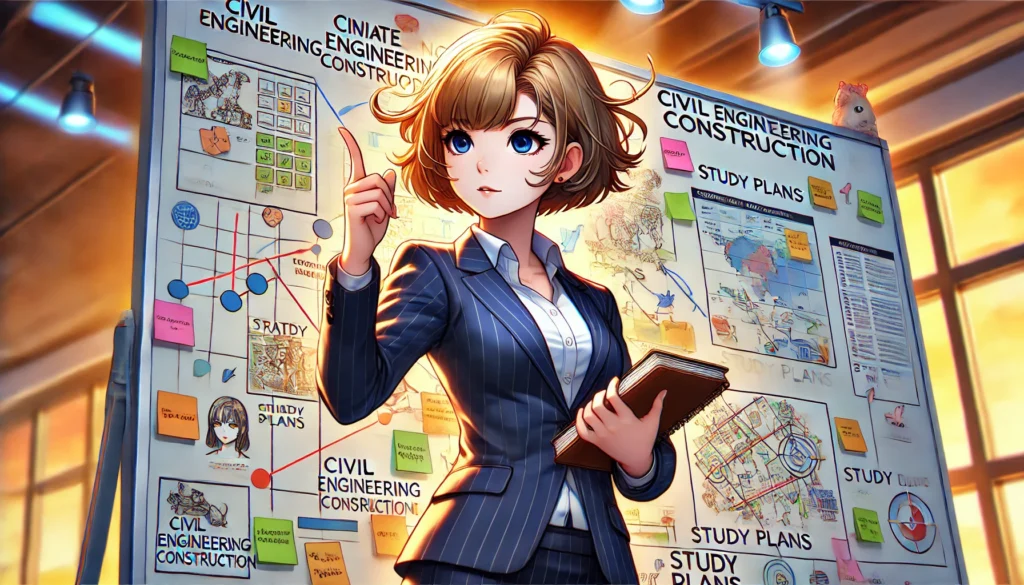
- 試験の難易度を知りたい人必見!合格への道は?
- 合格の見込みは?自分にチャンスがあるか判断しよう!
- 資格の価値がスゴい!取得で得られるメリットとは?
- 勉強方法と対策のコツ!合格者はこう学んでいた!
- 勉強時間はどれくらい?効率重視で時間を使おう!
- 過去問を使って合格力UP!失敗しない使い方とは?
- 1級土木の年収は?転職するなら建設コンサルがおすすめ!
試験の難易度を知りたい人必見!合格への道は?

「そもそも1級土木施工管理技士って、どれくらい難しいの?」と不安を感じている方もいらっしゃると思います。そう感じるのはとても自然なことですよ。
実際のところ、この試験は専門的な知識と実務経験の両方が問われる難関資格に位置付けられています。特に、一次検定はマークシート形式ですが、出題範囲は土木工学や施工管理法、法規など広範囲に及びます。
一方、二次検定は記述式。ここでは自分の経験や工事内容について論理的に書く力が必要になります。単なる暗記だけでは対応が難しく、現場での実践力や状況判断の経験が問われるのが特徴です。
また、2024年度の一次検定の合格率は44.4%、二次検定は41.2%と、どちらも決して簡単とは言えない数字です。
ただし、合格率がゼロではないということは、正しい方法で準備すれば、あなたにも十分に合格できる可能性があるということなんですよ。
難易度が高いと聞くと不安に感じるかもしれませんが、逆に言えば、合格できればそれだけの価値と信頼を得られる資格です。計画的な学習と正確な情報収集を重ねていけば、あなたの力で乗り越えることができるでしょう。
不安があるからこそ、準備の第一歩を丁寧に踏み出してみてくださいね。
合格の見込みは?自分にチャンスがあるか判断しよう!

1級土木施工管理技士の試験に合格するためには、しっかりとした準備が欠かせません。あなたがこれから試験に挑もうとしているのであれば、「どうすれば合格の可能性を高められるか?」という視点で学習計画を立てることがとても大切ですよ。
まず意識したいのは、試験の全体像を把握することです。
一次検定はマークシート方式で、比較的知識ベースの問題が中心ですが、出題範囲が広いので苦手分野があると足を引っ張ってしまいます。ですから、最初は「どの分野が得意で、どこが苦手か」を把握するところから始めましょう。
次に、一次試験と二次試験の準備は並行して進めるのがおすすめです。
なぜなら、二次検定は実務経験に基づいた記述式問題が出題され、短期間での対策が難しいからです。あなたのこれまでの経験を棚卸しし、どんな工事に携わってきたか、どういうトラブルを解決してきたかなど、記述に使えるネタをストックしておきましょう。
さらに、合格に向けて自信をつけるには、過去問題の分析が鍵になります。単に解くだけでなく、「なぜその答えになるのか?」までしっかり理解することで、応用力がぐっと伸びますよ。
そしてもうひとつ大事なことは、無理のないスケジュールを立てること。途中で息切れしないためにも、仕事や家庭とのバランスを見ながら、継続できるペースを保つようにしてくださいね。
合格の可能性は、あなたの準備の質で大きく変わります。一歩ずつ確実に進んでいけば、きっと合格というゴールに近づけますよ。
資格の価値がスゴい!取得で得られるメリットとは?

1級土木施工管理技士の資格は、ただの「肩書き」ではありません。建設業界で働くあなたにとって、大きなチャンスと信頼をもたらしてくれるキャリアの武器になる資格です。
まず、この資格を取得することで得られるメリットは、仕事の幅が広がることです。たとえば、公共工事や大規模なインフラ案件など、資格保有者でなければ携われない現場も多く存在します。これは、技術者としての評価が明確に高まる瞬間でもありますね。
また、会社によっては1級の資格手当が支給されるほか、昇進や役職の条件としてこの資格が求められるケースもあります。つまり、年収アップやポジションアップにもつながる可能性があるんですよ。
一方で、会社側にとっても資格保有者の存在は重要です。
1級の有資格者がいなければ取れない工事や、監理技術者の配置義務を果たすために必要な人材として、あなたの存在が欠かせないものになります。
そう考えると、この資格は業界内での希少価値が高いこともよくわかりますよね。
もちろん、取得までの道のりは簡単ではありませんが、その分、合格した時のリターンも非常に大きいです。
「手間はかかっても、それだけの価値がある」と言える資格ですので、あなたが今、挑戦を考えているのなら、その選択は間違っていませんよ。
勉強方法と対策のコツ!合格者はこう学んでいた!

1級土木施工管理技士の合格を目指すなら、ただ勉強を始めるのではなく、効果的な方法を取り入れることが大切です。限られた時間の中で成果を出すには、ポイントを押さえた学習が必要になりますよ。
最初におすすめしたいのは、過去問を徹底的に活用することです。
過去の出題傾向から、よく問われるテーマや難易度の変化がつかめるようになります。何度も繰り返して解くことで、問題のパターンに慣れていく感覚も養われますよ。
また、過去問を使う際には、「ただ正解する」だけではなく、「なぜこの答えになるのか」をしっかり理解しましょう。間違えた問題を放置せず、解説を読んで納得できるまで深掘りする姿勢がとても大切です。
さらに、一次検定と二次検定では学び方が異なります。
一次は知識中心なので、インプットを重視し、図や表を活用した整理が有効です。
対して二次は記述力が求められるので、自分の経験をもとに文章を書く練習が欠かせません。最初はうまく書けなくても大丈夫。何度も書いて、添削を受けながら改善していけば自然と力がついてきますよ
時間管理もコツの一つです。勉強時間は「量」より「質」が大事ですが、習慣化することも忘れずに。毎日30分でも良いので、継続することで知識が定着しやすくなります。
あなたのペースで、無理のないスケジュールを組んで学習を進めていけば、合格はきっと見えてきます。焦らず、少しずつ積み上げていきましょうね。

勉強時間はどれくらい?効率重視で時間を使おう!

1級土木施工管理技士に合格するためには、それなりの勉強時間が必要です。多くの人が「どれくらい勉強すれば受かるんだろう?」と気になるところですよね。
一般的には、500〜600時間ほどの学習が必要とされています。これを聞いて「そんなに!?」と驚くかもしれませんが、1日2時間ペースならおよそ8〜9か月ほどで達成できる計算になります。
つまり、無理なくコツコツ続ければ、十分に目指せる範囲なんですよ。
ただし、大事なのは「時間数」だけではありません。スケジュール管理の工夫が合否を左右するポイントになります。例えば、最初の2〜3か月は基礎知識のインプットに集中し、その後は過去問や記述対策に重点を置くといったように、学習フェーズごとに目的をはっきりさせることが大切です。
スケジュールを立てるときは、完璧を目指さなくても大丈夫。仕事や家庭の予定に合わせて柔軟に見直せるように、ざっくりとした「週単位の目標」から始めてみてくださいね。
また、学習の記録を簡単に残しておくと、モチベーション維持にも役立ちます。「今日は30分だけどやれた!」という積み重ねが自信になっていくはずです。
あなたの生活スタイルに合ったスケジュールで、少しずつ積み上げていきましょう。毎日の積み重ねが、合格への確かな道となっていきますよ。
過去問を使って合格力UP!失敗しない使い方とは?

1級土木施工管理技士の勉強において、過去問題の活用は合格への近道と言っても過言ではありません。過去問を使った学習は、出題傾向の理解や実力チェックにも非常に効果的ですよ。
まずは、直近3〜5年分の過去問題を繰り返し解いてみてください。これにより、よく出題されるテーマや苦手な分野が見えてきます。重要なのは「正解できたかどうか」だけではなく、「なぜその選択肢が正しいのか」「なぜ他が違うのか」をしっかり理解することなんです。
間違えた問題は特に丁寧に分析しましょう。自分だけの「弱点ノート」を作ると、復習がスムーズになり、効率的な学習につながります。
さらに、試験直前には「年度別に時間を測って解く」方法もおすすめです。本番さながらの練習をすることで、時間配分や集中力の維持にも慣れていくことができますよ。
一方で、過去問に頼りすぎるのは注意が必要です。新しい出題形式や応用問題が出る可能性もあるので、
基本的な理解をおろそかにせず、参考書や講義動画などで補足学習することも忘れないでくださいね。
このように、過去問は「使い方次第」で大きな武器になります。焦らず丁寧に、自分に合ったやり方で活用していきましょう。
1級土木の年収は?転職するなら建設コンサルがおすすめ!

「1級土木施工管理技士を取ると、年収ってどれくらい上がるの?」と気になりますよね。実際、資格取得後には待遇が大きく変わるケースも少なくありません。
平均的な年収は、およそ500〜700万円前後と言われています。経験や地域、勤務先によって幅はありますが、大手ゼネコンや建設コンサルタント会社などでは、年収800万円以上を狙えることもあるんですよ。
特に注目したいのが「建設コンサルタント業界」への転職です。この分野では、土木施工の専門知識に加えて、現場経験を持った人材が非常に重宝されます。資格保有者であれば、設計や発注者支援業務、施工計画の策定など幅広い役割を任されることもあるんです。
また、公共インフラの整備や再開発プロジェクトなど、社会的な意義のある仕事に関わるチャンスが増えるのも魅力のひとつです。給与面だけでなく、やりがいを感じられる職場環境を探しているあなたにはぴったりかもしれませんね。
もちろん、転職にはタイミングや準備も必要です。ただ、1級の資格を持っていることで、選択肢の幅がぐんと広がるのは間違いありません。
もし今の職場でキャリアの伸び悩みを感じているなら、資格をきっかけに新しいフィールドに挑戦することも視野に入れてみてはいかがでしょうか? あなたの可能性は、まだまだ広がっていますよ。
一級土木施工管理技士合格率から見る試験の全体像まとめ

- 一級土木施工管理技士の合格率は一次と二次で大きく異なる
- 一次検定の合格率は概ね50〜60%で推移している
- 二次検定の合格率は30%台が多く、難易度が高い
- 2024年度は受験者増加の影響で一次合格率が44.4%に低下
- 合格基準は基本的に正答率60%以上とされている
- 記述式の二次検定は採点基準がやや曖昧なため対策が重要
- 合格発表は一次が8月中旬、二次が12月中旬に行われる
- 合格発表は公式サイトまたは郵送で確認可能
- 令和6年度から受験資格が緩和され19歳以上なら受験可能
- 資格取得後は大規模工事や公共工事に関与できるようになる
- 他の施工管理資格と比較しても難易度と価値が高い
- 過去問を活用することで出題傾向の理解と実力強化ができる
- 必要な勉強時間は500〜600時間が目安とされている
- 建設コンサル業界では資格保有者の年収が高い傾向にある
- 転職支援サービスを活用することでより良いキャリアを築ける
もしも転職をお考えなら・・・
「いきなり転職するのは不安…」と感じる方も、面談だけならリスクゼロ!
まずは話を聞いてみることから始めてみてください。
✅ 今すぐ【Re就活エージェント】の詳細を見る
















コメント