地方で建設コンサルタントとして働くことに興味はあるものの、
「ホワイト企業はあるのか?」「就職難易度は高いのか?」「仕事についていけないのでは?」と不安を感じていませんか?
また、「建設コンサルタントとゼネコン、どちらがいいのか?」と迷う方も多いでしょう。
実際、建設コンサルタントの仕事は決して楽ではありませんが、適切な企業を選べばホワイトな環境で働くことも可能です。
本記事では、建設コンサルタント ホワイト ランキングを紹介し、業界の現状や優良企業の見極め方について詳しく解説します。
さらに、「建設コンサルタントの仕事はなくなるのか?」という疑問にも答え、建設コンサル 日本最大手はどこか?三大会社とは? についても触れていきます。
特に、道路の建設コンサルタントの役割や、地方ならではの働き方のメリット・デメリットを詳しく解説。
「転職して後悔したくない」「建設コンサルタントはやめとけと言われる理由を知りたい」
そんな疑問を解消するために、業界のリアルな情報をお届けします。地方での建設コンサルタントの働き方について、しっかり理解し、自分に合ったキャリアを築いていきましょう!
読みたいところへジャンプできるよ!
こんな悩みを解決する記事を用意しました!

建設コンサルタント地方の働きやすさとは?

- 建設コンサルタントとゼネコン、どちらがいい?
- 建設コンサルタントのホワイト企業ランキング
- 優良企業の見極め方とは?
- 建設コンサルタントの三大会社とは?
- 道路の建設コンサルタントの特徴
建設コンサルタントとゼネコン、どちらがいい?

建設業界を目指す人にとって、「建設コンサルタント」と「ゼネコン」のどちらを選ぶべきかは、キャリアの方向性を決める重要な選択です。
この二つの職種は、社会インフラの整備に関わる点では共通していますが、仕事内容や求められるスキル、働き方が大きく異なります。
業務内容による違い
まず、建設コンサルタントは、プロジェクトの企画・設計・調査を主な業務とし、発注者(主に国や地方自治体)に対して最適な提案を行う仕事です。
都市計画や道路、橋梁、河川などのインフラ整備に関わるため、高度な技術力と専門知識が必要になります。施工自体は行わず、プロジェクトの上流工程に携わることが特徴です。
また、調査や設計の仕事が多いため、デスクワークが中心となります。
工事の規模によっては国土交通省やNEXCOなどの大手官庁の案件を担当することもあり、影響力の大きな仕事ができる魅力があります。
一方、ゼネコン(総合建設業者)は、建設コンサルタントが設計したものを実際に施工する役割を担います。
建築現場での管理が主な業務となり、現場監督として職人や協力会社をまとめ、工程管理や品質管理を行います。
施工段階では天候や現場の状況に応じて臨機応変な対応が求められるため、現場での実務経験が重要になります。体力的な負担は大きいものの、完成した建物やインフラを目の当たりにできる達成感がある仕事です。
- 理論的な思考力や設計に興味がある人 → 建設コンサルタント向き
- 現場での管理業務や実践的な仕事を好む人 → ゼネコン向き
建設コンサルタントは技術力と論理的思考が求められ、比較的デスクワークが多いため、落ち着いた環境で働きたい人に向いています。
一方、ゼネコンは体力勝負な部分が多く、現場での臨機応変な対応が必要なため、行動力があり、動きのある仕事を好む人に適しています。
労働環境の面でも違い
また、労働環境の面でも違いがあります。ゼネコンは納期に追われることが多く、現場の状況によっては深夜や休日も仕事をすることが珍しくありません。
そのため、長時間労働になりがちです。
一方、建設コンサルタントも納期に追われることはありますが、ゼネコンほど不規則な勤務体系にはならない傾向があります。
ただし、どちらの職種でも会社やプロジェクトの内容によって働き方は大きく異なるため、入社前に企業の実態をよく調べることが重要です。
収入面の違い
建設コンサルタントとゼネコンの給与水準は、大手企業であればどちらも比較的高めです。
ただし、ゼネコンの方が年収が高くなりやすい傾向があります。これは、ゼネコンでは夜間や休日の現場管理が必要となることが多く、その分の手当が加算されるためです。ただし、長時間労働になりがちな点は注意が必要です。
最終的には、自分がどのような働き方をしたいのか、どの分野でスキルを活かしたいのかによって決めることが重要です。設計やコンサルティングに興味があれば建設コンサルタント、現場での施工管理をやりたいならゼネコンが向いていると言えるでしょう。
建設コンサルタントのホワイト企業ランキング

建設コンサルタント業界は、激務のイメージを持たれることが多いですが、すべての企業が過酷な環境というわけではありません。実際には、ワークライフバランスを重視し、適正な労働環境を整備している企業も多く存在します。ここでは、ホワイト企業と評価される建設コンサルタント会社をランキング形式で紹介します。
1位:日本工営(にっぽんこうえい)
業界最大手の建設コンサルタント企業で、国内外のインフラプロジェクトに幅広く携わっています。技術力の高さと安定した経営基盤が強みで、福利厚生や労働環境の改善にも力を入れています。労働時間の管理が厳しく、過度な残業を防ぐ仕組みが整っている点が評価されています。
2位:パシフィックコンサルタンツ
都市計画や交通インフラを中心に手掛ける企業で、近年は働き方改革にも積極的に取り組んでいます。リモートワークやフレックスタイム制度を導入し、ワークライフバランスを重視する姿勢が評価されています。給与水準も高く、働きやすさと収入のバランスが取れているのが魅力です。
3位:建設技術研究所(CTI)
河川や道路、環境分野に強みを持つ大手コンサルタント企業。技術者の専門性を活かせる環境が整っており、定着率が高いのが特徴です。特に、研修制度が充実しているため、未経験者や若手社員のスキルアップがしやすい環境が整っています。
4位:オリエンタルコンサルタンツ
国土マネジメントや防災分野に強い企業で、行政との協力体制が充実しています。比較的長時間労働が少なく、休日の確保がしやすい点がホワイト企業として評価されています。また、社内の人間関係が良好で、働きやすい職場環境が整っています。
5位:セントラルコンサルタント
道路、交通、橋梁、河川などの分野で幅広く事業を展開している企業。社員の満足度が高く、給与水準も比較的高めです。業務量のコントロールがしっかりされており、過度な負担がかかりにくい体制が整っています。
ホワイト企業を選ぶポイント
建設コンサルタント業界でホワイト企業を選ぶ際には、以下の点をチェックすると良いでしょう。
- 残業時間の管理:長時間労働が常態化していないか?
- 休日取得率:週休2日制が守られているか?
- 福利厚生の充実度:住宅手当や資格支援制度が整っているか?
- 社員の口コミや評判:実際の社員の声を確認する
建設コンサルタント業界は「激務」というイメージを持たれがちですが、企業選びを慎重に行えば、安定した環境で働くことも可能です。ホワイト企業を見極め、自分に合った働き方を実現しましょう。
優良企業の見極め方とは?
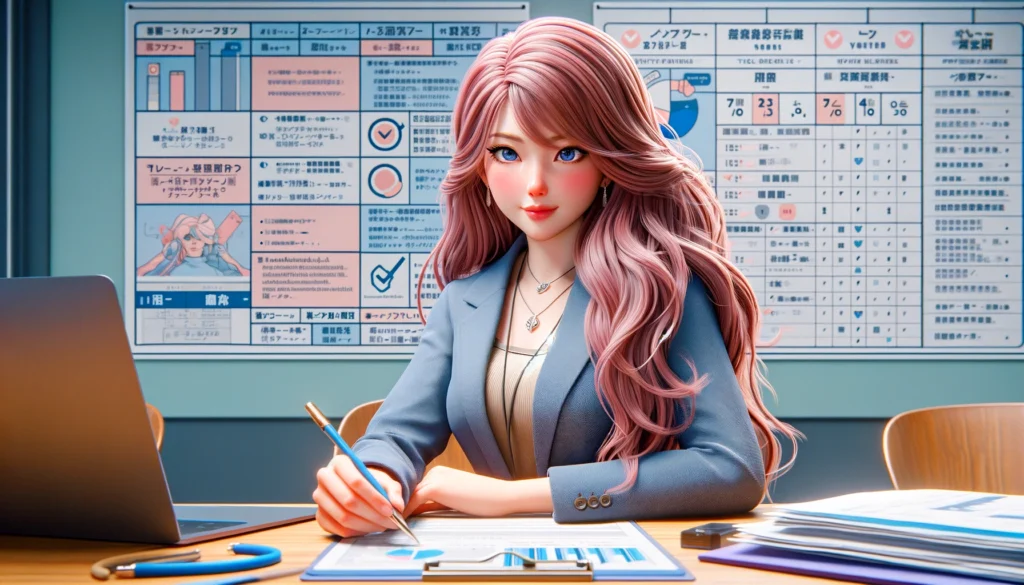
建設コンサルタント業界での就職や転職を考える際、どの企業を選ぶかは非常に重要です。
しかし、「優良企業」と一言でいっても、企業ごとに強みや特徴が異なるため、自分にとって働きやすい企業を見極めることが大切です。
ここでは、建設コンサルタント業界で優良企業を選ぶためのポイントを詳しく解説します。
1. 労働環境の健全性(残業時間・休日取得)
建設コンサルタント業界は納期に追われることが多く、長時間労働が発生しやすい業界です。
しかし、企業によっては労働時間の管理がしっかりされており、過度な残業を抑える仕組みを整えている企業もあります。
例えば、月の残業時間が30時間以内に抑えられている企業は、比較的ワークライフバランスを保ちやすい傾向にあります。
また、有給休暇の取得率や週休2日制がしっかり守られているかも重要なポイントです。業務が忙しい時期でも、会社がしっかりと休日を確保できる仕組みを作っているかどうかを確認しましょう。
2. 給与・賞与の水準
給与は企業の魅力を判断する重要な指標の一つです。建設コンサルタント業界の平均年収は約498万円とされていますが、優良企業では年収600万円以上も十分に可能です。
特に、賞与や能力給制度が整っている企業は、努力や実績が給与に反映されやすいため、モチベーションを保ちやすくなります。
また、給与だけでなく、退職金制度や福利厚生(住宅手当・資格取得支援など)の有無もチェックポイントです。企業の公式サイトや転職口コミサイトで、実際の給与水準や福利厚生の内容を確認しましょう。
3. 企業の安定性と将来性
優良企業を見極める際、企業の財務状況や市場でのポジションを確認することも重要です。特に、売上高が安定している企業は長期的なキャリアを築きやすいといえます。
例えば、業界トップの日本工営や建設技術研究所は、売上高が700億円以上と、安定した経営基盤を持っています。
また、企業が成長しているかどうかも重要な判断材料です。近年では、ICTやAIを活用した建設技術の開発に力を入れている企業が成長を続けています。将来的な発展が期待できる企業かどうかを見極めることも、就職・転職先を選ぶ際のポイントです。
4. 企業文化と職場環境
職場環境が良いかどうかも、優良企業を見極める上で欠かせないポイントです。例えば、社員同士のコミュニケーションが円滑であるか、若手社員の教育体制が整っているかといった点は、働きやすさに直結します。
また、建設コンサルタント業界では、縦割りの文化が強い企業と、部門間の連携が活発な企業が存在します。仕事の進め方や職場の雰囲気が自分に合っているかを確認することも重要です。企業の口コミサイトや、OB・OG訪問を活用して、職場環境の実態をリサーチしましょう。
5. どんなプロジェクトに携われるか
建設コンサルタント企業ごとに、得意とする分野が異なります。国土交通省やNEXCOなどの大規模案件に関われる企業もあれば、地方自治体の案件に特化した企業もあります。
大手企業では、国内外の大型プロジェクトに携わる機会が多く、最新の技術やノウハウを学ぶことができるメリットがあります。一方、地方の企業では、地域密着型の仕事が多く、顧客と長期的な関係を築きながら働ける点が魅力です。自分のキャリアプランに合ったプロジェクトに携われる企業を選びましょう。
\第二新卒・既卒・フリーター向け|20代向け転職エージェント/
あなたの転職を全力でサポートする転職エージェント
まとめ
優良企業を見極めるためには、労働環境、給与、企業の安定性、企業文化、プロジェクトの種類など、複数の観点から判断することが重要です。建設コンサルタント業界は企業ごとに特色が異なるため、自分にとって最適な環境を選ぶことが、長期的に満足できるキャリアを築く鍵となります。
建設コンサルタントの三大会社とは?

建設コンサルタント業界には数多くの企業がありますが、特に業界を代表する三大会社と呼ばれる企業が存在します。それが、日本工営・建設技術研究所・オリエンタルコンサルタンツの3社です。
これらの企業は、売上高・技術力・業界内での影響力においてトップクラスの実績を誇り、建設コンサルタントを目指す人にとって有力な選択肢となります。
1. 日本工営(にっぽんこうえい)
日本工営は建設コンサルタント業界最大手であり、国内外のプロジェクトを手掛ける総合コンサルタント企業です。売上高は1,300億円を超え、建設コンサルタントの中でも圧倒的な規模を誇ります。
特徴としては、国内だけでなく海外のインフラ開発にも積極的であることが挙げられます。特に、アジアやアフリカの発展途上国での都市開発、交通インフラ整備など、国際的な案件が多いのが強みです。グローバルな仕事に携わりたい人にとって、魅力的な企業といえます。
2. 建設技術研究所(CTI)
建設技術研究所は、道路・河川・防災・環境分野に強みを持つ建設コンサルタントで、特に公共インフラの計画や設計を多く手掛けています。売上高は約744億円と、業界内で高いシェアを占めています。
また、官公庁との関係が深く、国や地方自治体からの案件を多く受注しています。そのため、公共事業を通じて社会貢献をしたいと考える人には適した企業といえます。
3. オリエンタルコンサルタンツ
オリエンタルコンサルタンツは、都市計画や交通インフラ整備に強みを持つ企業です。売上高は約773億円で、大規模な道路や橋梁の設計、行政支援業務などを幅広く手掛けています。特に、NEXCO(高速道路会社)関連の案件が多いため、道路インフラに興味がある人にはおすすめの企業です。
まとめ
建設コンサルタント業界の三大会社である日本工営・建設技術研究所・オリエンタルコンサルタンツは、それぞれ異なる強みを持ち、業界内での影響力が大きい企業です。自分のキャリアや興味に合った企業を選び、建設コンサルタントとしてのキャリアを築いていきましょう。
道路の建設コンサルタントの特徴

道路の建設コンサルタントは、社会インフラの根幹を支える重要な役割を担っています。道路は、人や物の流れをつくる大動脈であり、その計画・設計・維持管理を担う建設コンサルタントは、地域社会の発展に不可欠な存在です。ここでは、道路の建設コンサルタントの主な業務内容や特徴について詳しく解説します。
1. 道路の建設コンサルタントが関わる業務とは?
道路の建設コンサルタントが担当する業務は多岐にわたりますが、大きく以下の3つに分類されます。
- 計画・設計業務
- 新しい道路を建設する際のルート選定や設計
- 交通量調査をもとに、道路の幅員や交差点の形状を決定
- 高速道路や都市部の道路整備計画の立案
- 維持管理・補修業務
- 既存の道路の点検や診断を行い、老朽化した部分の改修を計画
- 災害発生時の応急復旧や長期的な復旧計画の立案
- 交通の安全性を確保するための改善提案(ガードレールの設置や交差点の改良など)
- 環境対策や都市計画との連携
- 道路建設による環境影響評価(騒音や振動対策など)
- 省エネ・脱炭素社会を意識した新技術の導入(EV専用道路、太陽光発電道路など)
- スマートシティ構想と連携した道路設計(自動運転技術との融合)
道路は全国どこにでも存在するため、地方自治体から国レベルの機関まで、幅広い発注者の依頼を受けることが特徴です。
2. 道路の建設コンサルタントの強みとやりがい
道路の建設コンサルタントは、国土交通省やNEXCO(高速道路会社)などの大型案件に関わる機会が多く、スケールの大きなプロジェクトに携われるのが特徴です。例えば、新規の高速道路建設プロジェクトや、大規模なバイパス整備事業などは、社会的な影響も大きく、技術者としてのやりがいを感じられます。
また、人々の生活に直結する仕事である点も魅力のひとつです。例えば、新たな道路ができることで交通渋滞が解消されたり、災害時の避難ルートが確保されたりするなど、社会貢献度が高い仕事といえます。
加えて、ICT技術やAIを活用した「スマート道路」への取り組みも進んでおり、今後ますます技術革新が求められる分野でもあります。これにより、新しい技術を学び続けることができ、技術者としての成長を実感しやすい職種でもあります。
3. 道路の建設コンサルタントが求められる理由
道路インフラは一度作れば終わりではなく、長期的な維持管理が不可欠です。特に日本では、戦後に建設された高速道路や国道の老朽化が進んでおり、橋梁やトンネルの点検・補修ニーズが増加しています。そのため、道路の建設コンサルタントの需要は今後も安定すると考えられます。
また、近年では「コンパクトシティ構想」や「スマートモビリティ」など、新しい都市計画との連携も求められています。例えば、高齢化社会に対応した歩行者優先の道路設計や、MaaS(Mobility as a Service)との連携を考慮した道路整備など、従来の道路設計に加えて、新たな視点が求められるようになっています。
まとめ
道路の建設コンサルタントは、社会基盤を支える重要な仕事であり、スケールの大きなプロジェクトに関われるやりがいのある職種です。また、道路インフラの老朽化対策やスマートシティの推進により、今後も安定した需要が見込まれています。社会貢献性が高く、新技術の導入にも積極的な分野であるため、インフラ整備に興味がある人にはおすすめの職種といえるでしょう。
建設コンサルタント地方でのキャリアと将来性

- 就職難易度はどのくらい?
- 仕事についていけないと感じる理由
- 建設コンサルタントの仕事はなくなるのか?
- 転職して後悔しないためのポイント
- やめとけと言われる理由と実際の働き方
- 建設コンサル日本最大手はどこ?
- 自分に合った企業の選び方とは?
就職難易度はどのくらい?

建設コンサルタント業界の就職難易度は、企業の規模や専門分野によって異なります。一般的に、大手建設コンサルタント企業は就職難易度が高く、中小規模の企業は比較的入りやすい傾向にあります。しかし、どの企業も技術者としての専門性が求められるため、知識やスキルを持っているかが重要なポイントになります。
1. 大手建設コンサルタント企業の就職難易度
大手企業(日本工営、建設技術研究所、オリエンタルコンサルタンツなど)は、倍率が高く、専門知識や技術資格が求められることが多いです。特に、国土交通省やNEXCOなどの官公庁の案件を多く扱っている企業は、技術力の高い人材を求めています。
また、大手企業は新卒採用においても学歴や専攻を重視する傾向があり、特に土木・環境工学系の学部出身者が有利になります。加えて、技術士補やRCCM(シビルコンサルタント資格)などの資格を持っていると、採用で優遇されることがあります。
2. 中小規模の建設コンサルタント企業の就職難易度
一方、中小規模の建設コンサルタント企業は、大手ほどの知名度はないものの、地域密着型の事業を展開しているため、比較的採用枠が多い傾向にあります。特に、地方の建設コンサルタント企業では、地元に密着した案件が多く、地元出身者が優遇されるケースもあります。
また、中小企業では、新卒だけでなく中途採用にも積極的な企業が多く、即戦力となる経験者の採用が活発です。例えば、ゼネコンや自治体での土木関連の経験があると、転職がスムーズになることもあります。
3. 建設コンサルタントの就職に有利なスキル・資格
就職難易度を下げるためには、技術士補・RCCM・測量士などの資格取得が大きな武器になります。また、CADやGIS(地理情報システム)などのスキルを持っていると、即戦力として評価されやすくなります。
さらに、近年ではBIM/CIM(3D設計技術)が重要視されており、これらのスキルを習得していると、競争力が高まります。
まとめ
建設コンサルタントの就職難易度は、大手企業ほど高く、中小企業ほど入りやすい傾向にあります。ただし、どの企業でも技術力が重視されるため、資格やスキルを磨くことが就職成功の鍵となります。
仕事についていけないと感じる理由

建設コンサルタント業界では、「仕事についていけない」と感じる人が少なくありません。その背景には、業務の専門性の高さや労働環境、求められるスキルの多様さなど、さまざまな要因が影響しています。
ここでは、建設コンサルタントの仕事についていけないと感じる主な理由を詳しく解説します。
1. 専門知識の要求が高い
建設コンサルタントは、道路・橋梁・河川・上下水道などの社会インフラを設計・計画する仕事です。そのため、土木工学をはじめとする専門知識が不可欠です。特に、新卒や異業種からの転職者にとっては、業務で必要な知識が多すぎて理解が追いつかないと感じることがよくあります。
さらに、発注者である官公庁(国土交通省や地方自治体)からの依頼に応じて、法律や規格、施工管理に関する詳細な知識も必要となります。
例えば、道路設計であれば「道路構造令」、河川関係であれば「河川法」といった法律を熟知していなければなりません。
これらの情報を短期間で習得するのは容易ではなく、「知識が足りない」と感じて仕事についていけなくなることがあります。
2. 納期に追われるプレッシャー
建設コンサルタントの仕事はプロジェクトごとに納期が決まっており、そのスケジュール管理が非常にシビアです。官公庁や民間企業からの発注が多く、期限を守ることが厳しく求められます。そのため、短期間で大量の業務をこなさなければならず、精神的なプレッシャーを感じやすい仕事でもあります。
特に、経験の浅い人ほど作業効率が悪くなりがちで、想定していた時間内に業務を終えられずに焦ることが多くなります。
設計や調査の業務は専門的なスキルを必要とするため、作業スピードが遅いとチーム全体に影響が出ることもあり、プレッシャーを感じる原因になります。
3. 上司やクライアントとのコミュニケーションの難しさ
建設コンサルタントは、発注者である国や地方自治体、民間企業との折衝が多い仕事です。クライアントの要望を正確に理解し、技術的な課題を解決する提案をしなければならないため、コミュニケーション能力が求められます。
しかし、技術者としての専門知識が求められる一方で、交渉力やプレゼンテーション能力も必要になるため、「技術的なことは分かるけれど、クライアントとうまく話せない」という人が仕事についていけないと感じることがあります。また、社内では上司や先輩との関係も重要で、業務の進め方や報告の仕方が分からず、指導を受ける機会が少ないと孤立しがちです。
4. 長時間労働とワークライフバランスの難しさ
建設コンサルタント業界は、納期が厳しいために長時間労働になりやすい傾向があります。特に大手企業では、プロジェクトの規模が大きく、納期前には終電帰りや徹夜が発生することもあるため、体力的・精神的に厳しくなることがあります。
また、業務量が多いために新入社員や若手社員が自分のペースで仕事を覚える余裕がないことも多く、「常に追われている」と感じてしまいます。その結果、モチベーションが低下し、仕事についていけないと感じるようになります。
5. 仕事の内容が幅広く、全てを覚えきれない
建設コンサルタントの仕事は、「調査・設計・施工管理・維持管理」など多岐にわたります。企業によっては、業務の専門性が高い分野に特化している場合もありますが、小規模な企業では、一人が複数の業務を担当しなければならないことも多いです。
例えば、道路設計を専門にしていた人が、ある日突然、河川の設計を担当することになると、これまでの知識が通用せず、最初から勉強し直さなければなりません。
このように、業務の幅が広いため、「やることが多すぎてついていけない」と感じる人も少なくありません。
まとめ
建設コンサルタントの仕事についていけないと感じる主な理由には、専門知識の多さ、納期の厳しさ、コミュニケーションの難しさ、長時間労働、業務の多様性などが挙げられます。
しかし、最初は誰もが苦労するものなので、焦らずに少しずつ知識を身につけることが大切です。スキルアップを続けることで、自信を持って仕事に取り組めるようになるでしょう。
\第二新卒・既卒・フリーター向け|20代向け転職エージェント/
建設コンサルタントの仕事はなくなるのか?

近年、技術革新や業界の変化が進む中で、「建設コンサルタントの仕事は将来なくなるのでは?」と不安を抱く人もいます。
しかし、結論から言うと、建設コンサルタントの仕事が完全になくなることは考えにくいです。その理由を詳しく解説します。
1. インフラ維持管理の需要は今後も増加する
日本の社会インフラは、高度経済成長期に整備されたものが多く、老朽化が深刻な問題となっています。橋梁、道路、ダム、上下水道など、さまざまなインフラが耐用年数を迎えており、これらの維持管理や改修を担う建設コンサルタントの需要は高まり続けるでしょう。
特に、災害対策や都市防災の分野では、河川整備や耐震補強などの計画が増えており、建設コンサルタントの役割はますます重要になっています。
2. AIや自動化が進んでも技術者の判断が不可欠
建設業界では、AIや自動化技術が導入され、業務の効率化が進んでいます。しかし、建設コンサルタントの業務は、単純作業ではなく、高度な専門知識と判断力を必要とする仕事が多いため、完全に機械に置き換わることはありません。
例えば、設計やシミュレーションはAIによって部分的に自動化されていますが、最終的な判断やクライアントとの調整は人間のエンジニアが行う必要があります。
3. スマートシティや新技術の発展で新たな需要が生まれる
今後は、スマートシティやカーボンニュートラルの実現に向けたインフラ整備が進みます。これにより、建設コンサルタントには新たな役割が求められ、新しい分野での活躍の場が増えていくでしょう。
まとめ
建設コンサルタントの仕事は、技術革新によって変化する可能性はありますが、完全になくなることはありません。むしろ、新たな需要が生まれ、より多様な分野で活躍できる職種となるでしょう。
転職して後悔しないためのポイント

建設コンサルタントへの転職を考えている人の中には、「本当に転職して大丈夫だろうか?」と不安を感じる人も多いでしょう。
転職は人生の大きな選択の一つであり、慎重に進めるべきものです。実際に転職してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
1. 転職の目的を明確にする
転職する理由を曖昧にしたままでは、「今の職場が嫌だから」「何となく新しい環境に行きたいから」といった理由で決断してしまいがちです。
しかし、目的がはっきりしていないと、転職後に「思っていたのと違う」と感じる可能性が高まります。
例えば、以下のように具体的に考えてみましょう。
- ワークライフバランスを改善したいのか?
- 専門性を深めたいのか、それとも幅広いスキルを身につけたいのか?
- 給与や待遇を良くしたいのか?
- 勤務地を変えたいのか?
こうした目的を明確にしておけば、転職先の選定がスムーズになり、後悔を減らすことができます。
2. 企業の実態を事前に調査する
建設コンサルタント業界は、企業ごとに働き方や文化が大きく異なります。転職前に「この会社は本当に自分に合っているのか?」をしっかり調べることが重要です。
以下の点を確認すると、転職後のミスマッチを防ぐことができます。
- 残業時間・休日取得率:求人情報や口コミサイトを参考に、長時間労働が常態化していないかチェックする。
- 企業の財務状況:売上高や業績推移を調べ、安定している会社かどうかを確認する。
- 離職率:離職者が多い会社は、労働環境や人間関係に問題がある可能性が高い。
- 面接での質問:面接時に「現在の社員の平均的なキャリアパスは?」など具体的な質問をして、実態を把握する。
転職先の情報をしっかり調べることで、「想定外のブラック企業だった」という後悔を防ぐことができます。
3. 必要なスキルや資格を身につける
建設コンサルタントは、専門性が求められる職種です。そのため、転職前に「自分が即戦力として活躍できるか?」を考えることが大切です。
例えば、以下の資格やスキルを持っていると、転職先での評価が高くなり、スムーズに仕事に適応できます。
- 技術士補やRCCM(シビルコンサルタント資格)
- CADソフトの操作スキル(AutoCAD、Civil 3D など)
- GIS(地理情報システム)の知識
- BIM/CIM(3D設計技術)の活用スキル
特に、これまでゼネコンなどで施工管理をしていた人が建設コンサルタントへ転職する場合、設計や計画業務の知識が不足していることが多いです。事前に学習しておけば、転職後に「ついていけない」と感じるリスクを減らせます。
土木CADの資格取得するなら、
諒設計アーキテクトラーニングは通信講座で資格を簡単に取得できます!
4. 転職後のキャリアプランを考えておく
転職はゴールではなく、新しいキャリアのスタートです。そのため、転職先でどのようにキャリアを積んでいくのかを考えておくことが大切です。
例えば、数年後に管理職を目指すのか、それとも専門性を高めてスペシャリストになるのかといった方向性を持っておくと、転職後もモチベーションを維持しやすくなります。
まとめ
転職して後悔しないためには、目的を明確にし、企業の実態を調査し、必要なスキルを身につけ、キャリアプランを考えることが重要です。しっかり準備をして転職すれば、新しい環境での成功につながります。
やめとけと言われる理由と実際の働き方

建設コンサルタントの仕事は、「やめとけ」と言われることが少なくありません。特に、長時間労働や専門性の高さ、納期の厳しさなどが理由として挙げられることが多いです。
しかし、すべての企業や職場が厳しいわけではなく、会社選びや働き方次第では充実したキャリアを築くことも可能です。ここでは、「やめとけ」と言われる理由と、実際の働き方について詳しく解説します。
1. やめとけと言われる主な理由
(1) 長時間労働になりやすい
建設コンサルタントの仕事は、プロジェクトごとに厳しい納期が設定されており、特に年度末は激務になりやすい傾向があります。国や地方自治体の発注業務が多く、予算消化の関係で3月に納品が集中することが要因の一つです。
(2) 専門知識が必要で、学ぶことが多い
建設コンサルタントは、土木設計や環境調査、インフラの維持管理など多岐にわたる知識が必要になります。新卒や未経験者の場合、「覚えることが多すぎてついていけない」と感じることも少なくありません。
(3) 給与が労働時間に見合わないことがある
給与水準は比較的高いものの、業務量が多いため「時給換算すると割に合わない」と感じる人もいます。
ただし、近年は働き方改革が進み、ホワイトな企業も増えてきているのが現状です。
2. 実際の働き方と改善策
(1) 会社選びで労働環境は大きく変わる
同じ建設コンサルタントでも、企業によって労働環境は大きく異なります。例えば、日本工営や建設技術研究所などの大手企業では、ワークライフバランスを重視する動きが強まっています。
また、地方の建設コンサルタントでは、比較的落ち着いた環境で働ける場合もあります。
(2) 資格やスキルを身につければキャリアの選択肢が広がる
技術士やRCCMを取得すれば、より良い条件の企業への転職や、独立も視野に入れることができます。
また、BIM/CIMなどの最新技術を学ぶことで、より専門性の高いポジションを狙うことも可能です。
まとめ
「やめとけ」と言われるのは、長時間労働や専門性の高さが理由です。しかし、会社選びを慎重にし、スキルを磨けば、充実したキャリアを築くことも可能です。自分に合った働き方を見つけることが、建設コンサルタントとして成功する鍵となります。
\第二新卒・既卒・フリーター向け|20代向け転職エージェント/
建設コンサル日本最大手はどこ?

建設コンサルタント業界には多くの企業が存在しますが、その中でも「日本最大手」とされる企業はいくつかあります。
建設コンサルタントは、国や地方自治体から発注を受け、道路や橋梁、河川、上下水道などのインフラ整備に関わる仕事を担う企業です。
売上高や従業員数、受注案件の規模を基準にすると、業界のトップに位置するのは「日本工営」です。
1. 日本最大手の建設コンサルタント「日本工営」
日本工営(にっぽんこうえい)は、1946年に設立され、国内外のインフラ整備に関わる総合建設コンサルタント企業です。売上高は1,300億円以上(2023年度)と、業界内で圧倒的な規模を誇ります。
日本工営の特徴として、国内の公共インフラだけでなく、海外のインフラ開発プロジェクトにも積極的に関与している点が挙げられます。特に、アジアやアフリカの発展途上国における道路やダム、発電所の建設に関わるプロジェクトを多数手掛けており、国際的な建設コンサルタント企業としての地位を確立しています。
また、日本工営は官公庁(国土交通省やNEXCOなど)の案件が多く、安定した受注を確保しているため、長期的に安定した業績を維持しています。
2. その他の主要な大手建設コンサルタント企業
日本工営以外にも、日本を代表する建設コンサルタント企業がいくつかあります。
- 建設技術研究所(CTI)
- 売上高:約744億円(2023年度)
- 主に河川、道路、環境分野のインフラ整備に強みを持つ
- 国や地方自治体との関係が深く、公共事業を中心に事業展開
- オリエンタルコンサルタンツ
- 売上高:約773億円(2023年度)
- 道路や交通インフラに特化した事業展開
- 特にNEXCO関連の業務が多く、高速道路の設計・管理を担当
- パシフィックコンサルタンツ
- 売上高:約512億円
- 都市計画や交通インフラ、環境保全プロジェクトなどに強み
- 海外展開も進めており、国内外のインフラ整備に関与
これらの企業は、日本工営と並び、建設コンサルタント業界をリードする存在であり、業界全体の発展を支えています。
3. 日本最大手の建設コンサルタントに就職するには?
大手建設コンサルタント企業への就職を目指す場合、以下のようなポイントを意識することが重要です。
- 土木工学や環境工学などの専門知識を身につける
- 技術士補やRCCMなどの資格取得を目指す
- インターンシップや企業説明会に積極的に参加する
- 研究室や大学の教授を通じて情報収集を行う
大手企業ほど応募者が多く、採用倍率も高くなるため、しっかりとした準備が必要になります。
まとめ
日本最大手の建設コンサルタント企業は、「日本工営」です。その他にも、建設技術研究所、オリエンタルコンサルタンツ、パシフィックコンサルタンツなどの大手企業があり、それぞれ異なる強みを持っています。
就職を目指す場合は、企業ごとの特徴を理解し、必要なスキルや資格を身につけることが重要です。
自分に合った企業の選び方とは?
建設コンサルタント業界で働く上で、自分に合った企業を選ぶことは非常に重要です。企業ごとに業務内容や社風、働き方が異なるため、適当に選んでしまうと「思っていた仕事と違った」と後悔する可能性が高くなります。ここでは、自分に合った企業を選ぶためのポイントを詳しく解説します。
1. 企業の業務内容を確認する
建設コンサルタントと一口に言っても、企業によって得意分野が異なります。例えば、道路設計に強い企業、河川整備が得意な企業、都市計画に特化した企業など、それぞれ専門分野があります。
例えば、以下のように考えてみましょう。
- 道路や橋梁の設計に興味があるなら? → オリエンタルコンサルタンツやパシフィックコンサルタンツ
- 河川や環境分野に関心があるなら? → 建設技術研究所(CTI)
- 海外のプロジェクトに関わりたいなら? → 日本工営
このように、自分の興味や専門分野に合った企業を選ぶことが重要です。
2. 企業の働き方や労働環境をチェックする
建設コンサルタント業界は、長時間労働になりやすい業界でもあります。しかし、企業によってはワークライフバランスを重視し、残業時間を減らす取り組みを行っているところもあります。
労働環境をチェックする際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 年間休日はどのくらいか?
- 月の平均残業時間は?
- 有給休暇の取得率は?
- 社員の定着率(離職率)は?
企業の公式サイトや口コミサイト、社員の評判を参考にすると、実態を把握しやすくなります。
3. キャリアアップのしやすさを考慮する
建設コンサルタントとして長く働く場合、キャリアアップのしやすさも重要なポイントです。
- 研修制度が整っているか?
- 資格取得支援があるか?
- 管理職への昇進がしやすいか?
特に、技術士やRCCMなどの資格取得を支援してくれる企業は、スキルアップしやすく、長期的なキャリア形成に有利です。
4. 企業の将来性を見極める
建設コンサルタント業界は、公共事業の発注が大きく影響するため、企業の安定性も重要なポイントです。売上高や業績推移を確認し、成長している企業かどうかをチェックしましょう。
まとめ
自分に合った企業を選ぶためには、業務内容、労働環境、キャリアアップのしやすさ、企業の安定性を総合的に考慮することが大切です。建設コンサルタント業界は企業ごとに特色が異なるため、自分の希望に合った会社を選び、充実したキャリアを築いていきましょう。
建設コンサルタント 地方での働き方と将来性
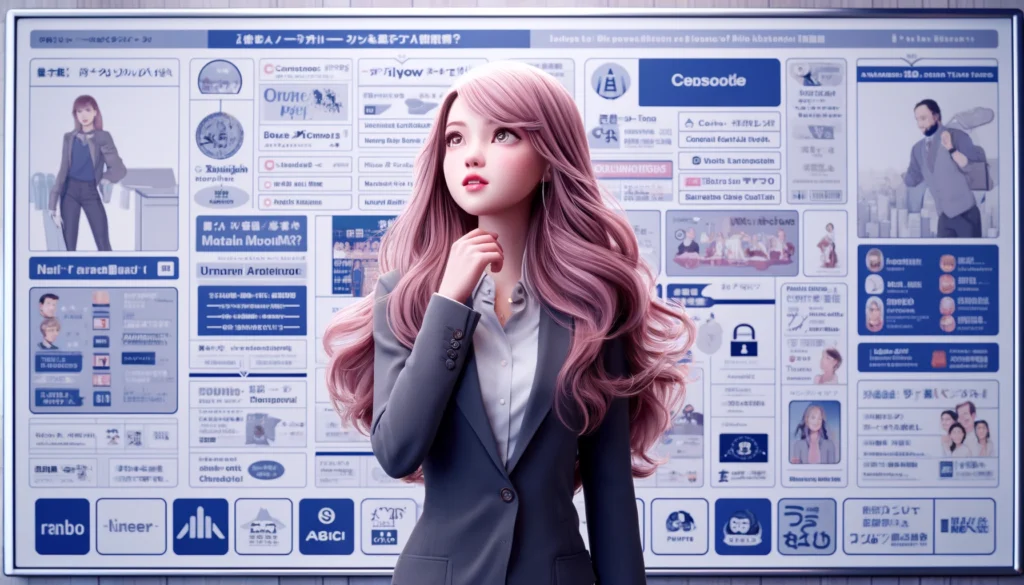
- 建設コンサルタントは設計・調査を行い、ゼネコンは施工を担う
- 地方の建設コンサルタントは地域密着型で、行政との関係が深い
- ゼネコンは体力的負担が大きく、建設コンサルタントはデスクワークが多い
- 建設コンサルタントのホワイト企業は、労働時間や福利厚生が整っている
- 優良企業は給与・労働環境・企業の成長性で見極めることが重要
- 日本工営・建設技術研究所・オリエンタルコンサルタンツが三大会社
- 道路の建設コンサルタントは国土交通省やNEXCO案件が多い
- 地方の建設コンサルタントはインフラ維持管理の需要が高まっている
- 大手建設コンサルタントは就職難易度が高く、専門資格が求められる
- 中小規模の地方企業は地域出身者が優遇されやすい傾向にある
- 仕事についていけないと感じる理由は専門知識の多さと納期の厳しさ
- AIや自動化が進んでも建設コンサルタントの判断力は不可欠
- 転職では企業の実態を調査し、キャリアプランを明確にすることが大切
- 「やめとけ」と言われるのは長時間労働や専門知識の負担が理由
- 地方の建設コンサルタントは安定性があり、働きやすさの面で優位な企業も多い
「いきなり転職するのは不安…」と感じる方も、面談だけならリスクゼロ!
まずは話を聞いてみることから始めてみてください。
✅ 今すぐ【Re就活エージェント】の詳細を見る















コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 建設コンサルタント 地方で安定したキャリアを築く方法とは? […]